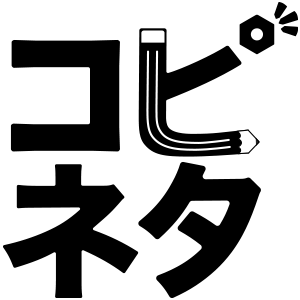売れるキャッチコピーの考え方・具体的な制作手順とアイデア発想法
キャッチコピーは、考え方を身に付ければどんどん書けるようになりますよ。
- そもそもキャッチコピーってなに?
- 売りたい商品があるんだけど、どんなキャッチコピーを書いたらいいかアイデアすら思いつかない
キャッチコピーを考えるときに大事なことはですね、課題解決が含まれているかどうかなんですね。
「限定〇〇」みたいな、型を覚えることよりもまず基本的な考え方を知った方が、キャッチコピーは書けるようになるんですね。
ぼくはフリーランスのWebライターとして仕事をしているんですけども、フリーランスになりはじめの頃はね、なかなか案件が受注できなくてですね、そりゃぁもう苦労したんですよ。
案件の応募数を増やしてもなかなか受注まで辿り着きませんし。クライアントを納得させるWebライティングの実績と自信はあるんです。
「どうしたら、クライアントにぼくの価値をわかってもらえるのだろうか」 思いつく限り、いろいろなアプローチを試していたんですけどね。
こんにちは、のざき寿(ひさし)といいます。元お笑い芸人です。
2020年宣伝会議コピーライター養成講座の卒業生です。金の鉛筆も結構もらいましたよ。キャッチコピーの公募にチャレンジしていたり、noteでエッセイを書いていたりします。
そこで、案件応募のメッセージにキャッチコピーを書いてみました。
「プログラミングもできるWebライター」なんて書きましたかね。
ぼくは前職、Webエンジニアとしてプログラミングをしていまして、Webライティング意外にも得意分野があることを冒頭でアピールしてみたのですね。
そしたら、クライアントから返事がきました。
ライティング以外にも、困っていることがあったんでしょうね。
キャッチコピーを書いたことで、自分の良さをアピールすることができましてね、初案件を獲得することができました。
多分、今までの応募メッセージは読まれていなかったのでしょう。たくさんある応募の中に埋もれてしまっていたんでしょう。
これがキャッチコピーの目的は、
「お客さんの注意を惹きつけてキャッチする」
これがゴールになります。
どれだけいい商品を作ったとしても、商品を知ってもらえてなければ手に取ってもらうことはありませんし、買うこともできませんからね。
まずは、キャッチコピーでお客さんの興味を惹きつけること。それが商品を売るために必要な、大事な一歩になると思うんですよね。
課題解決がイメージできるキャッチコピーを書こう
さっそくね、キャッチコピーの考え方を語っていこうと思うんですけどね、
まず、キャッチコピーで一番大事なことって何だと思います?
何が書いてあったらお客さんは「お!ええやん!」って、商品に興味を持ってもらえますでしょうかね?
それはですね「課題解決があるかどうか」です。
そのキャッチコピーから、お客さんが悩みを解決するイメージできるかどうかが重要なんですね。
このことをベネフィットと言いまして「お客さんがその商品を手にしたときに得られる解決」のを意味しています。
ちょっと具体例を挙げて解説していきますね。
「りんご」の課題解決・キャッチコピーを考えてみよう
売りたい商品が「りんご」だとしましょう。
どんなキャッチコピーのアイデアが思い浮かびますかね?
- 赤い?
- 甘い?
- 新鮮?
まずは見た目とか味とか、そういったことが思いつきますよね。
これらは「りんご」の特徴ですね。りんご(商品)そのものの見た目や性能を言い表した言葉、これをメリットと言いますね。
メリットではね、キャッチコピーになりにくいんです。当たり前のことを言ってるだけなので「あ、そう」で終わってしまうねですね。
ですからね、「りんご」の何を言ってあげたら、お客さんにの課題解決(ベネフィット)に繋がるかを考えていくんですね。
- お見舞いに持っていくといいですよ
- 朝ごはんの代わりにどうですか?
- おやつの代わりになりますよ
これらの言葉は、りんごの食べ方だったり用途だったりを提案していますよね。つまり課題解決でありアイデアになっているんです。
あなたの課題解決・キャッチコピーの考え方
もうひとつ具体例を挙げてみましょうか。
売りたい商品は「あなた」です。そう、自分自身。
そう考えると、就職活動や転職活動で自己PRを書く時にキャッチコピーの考え方が使えるわけです。
あなたは、就職したい企業に対して、どんな課題解決が提案できる人材ですか?
- 新卒で若い
- 最終学歴が国立大学卒で高学歴だ
- 〇〇業界で〇〇年の実務経験があるから経験が豊富
これらはメリットですね。その人自身が自分のことを語っているにすぎません。
課題解決をアピールするには、相手の視点に立つことが大事になってきます。
- 前職で売り上げ実績があるので、売上に貢献できる
- 人をまとめられる・リーダーシップがとれる
- 丁寧な仕事でミスが少ないから安心して仕事を任せられる
これらは、採用側に立って考えられていますよね。「もうちょっと具体的に話を聞いてみようかな」となるわけです。企業が欲しているのは、いつだって課題解決につながる人材ですから。
就職活動のエントリーシート・転職活動の履歴書は、キャッチコピーの考え方を取り入れると、書類審査に受かりやすくなると思いますよ。
こうして課題解決の視点でキャッチコピーを考えていくと、アイデアはどんどん出てきますよ。このことをね、キャッチコピーでは「切り口(What to say)」と言います。
次は、「切り口(What to say)」について詳しく解説していきますね。
キャッチコピーを考え方はたったふたつ
では、課題解決につながるキャッチコピーを考えるためには、どのようなアプローチでもって考えていくほうがいいのか、そこんところをお話ししたいと思います。
もう、とってもシンプルですよ。
売りたい商品に対して、
- 何を言うか(What to say)
- どう言うか(How to say)
このふたつさえ覚えておけば大丈夫です。間違い無いです。
ぼくがコピーライター養成講座で教わったことは、このふたつだけと言っても過言ではないですから。
では、詳しく解説していきますね。
何を言うか(What to say)の考え方
何を言うか(What to say)は、
「商品の何をアピールしたら魅力がより伝わるか」です。
要するに、商品訴求の切り口を考えることを言います。
またもや「りんご」が、あなたの売りたい商品だとしてね、
- お見舞いに持っていきませんか?
- 朝ごはんの代わりにどうですか?
- おやつの代わりにいかがでしょう?
これらは「りんご」が課題解決につながる場面の提案でした。そうそう、ベネフィットですよね。ベネフィットは「キャッチコピーの切り口」になっていたんですね。
つまりベネフィットは、「何を言うか(What to say)」です。
「何を言うか(What to say)」に必要な要素はですね、
- 共感がある
- 驚きや発見・気づきがある
- 納得できて・モヤモヤがスッキリする
こんなことを言われたとき、人は興味や関心を持つんですね。
人の注意を惹くとはつまり、人の心・感情を動かすことなのですね。キャッチコピーの「キャッチ」は文字通り「お客さんの心を掴む」という意味なんですね。
「りんご新鮮で甘くておいしいよー」と言っても、お客さんにしてみたら「そんなもんわかっとるわ」としかならないわけです。それでは「切り口」になってないんですよね。
切り口はキャッチコピーの出発点になるので、キャッチコピーを考える上でもっとも重要といえます。
この用語を知っているだけでも「おお!キャッチコピー書いたことあるんだな」と思われるので覚えておきましょう。
どう言うか(How to say)の考え方
さて、「何を言うか(What to say)」のままでは、キャッチコピーとして味気ないですよね。
なので、切り口に対してね「どう言うか(How to say)」を考えて、お客さんに刺さるキャッチコピーに言葉を変えていくわけですね。
要するに、「どう言うか(How to say)」をもうちょっと親しみやすい言葉に変えていくことが「何を言うか(What to say)」です。
さぁ、コピーライターの腕の見せ所ですよ!
「りんご」の切り口は以下の要素でしたね。
- お見舞いに持っていきませんか?
- 朝ごはんの代わりにどうですか?
- おやつの代わりにいかがでしょう?
これらの切り口をもとに、お客さんが「りんご」の具体的な利用シーンがイメージできるような言葉を考えていきます。
- 無機質な病室に彩りを
- シャキッとしたい二日酔いの朝に
- 食べすぎても大丈夫なおやつ
どうでしょうかね?
気づきや発見、共感がありましたかね?あ、もちろんこれらがいいキャッチコピーなんてひとことも言ってはないですよ。
一発でいいキャッチコピーに辿り着ければいいんですが、簡単ではないんですね。
だってプロのコピーライターでさえ、ひとつの商品にたいして100本くらいのキャッチコピーを書くっていうんですから。宣伝会議コピーライター養成講座の講師陣が言っていましたからね。
そこで次は、キャッチコピー制作工程・考え方について解説していきますね。
キャッチコピーの制作工程と考え方
「たまたま良いキャッチコピーを思いついた!」
できるだけこれを無くしたいわけです。
たまたまではなくて、狙っていいキャッチコピーを書きたいわけですよね。
センスとか才能で片付けてしまっては勉強する意味がないですから、ここからはキャッチコピーの考え方をもとに、制作プロセスについて解説していきますね。
キャッチコピーの考え方は、みっつのプロセスに分かれています。
- キャッチコピーを書く
- キャッチコピーを選ぶ
- キャッチコピーを磨く
シンプルですね。
この手順に沿ってキャッチコピー考えていけば、ある程度のクオリティーを担保できます。
ではひとつひとつ解説していきますね。
キャッチコピーをたくさん書く
「そりゃそうだろ!」ってことを言っているのはわかっています。わかってて、言っていますから。
でもね、キャッチコピーをたくさん書けるってことは、コピーライターにとってものすごく重要な資質なんですよ。
では、
100本書いたキャッチコピーの中から、1本だけ選ぶのか。
それとも、5本書いたキャッチコピーの中から、1本を選ぶのか。
どっちがいいキャッチコピーに辿り着くと思います?
前者ですよね、数多の候補の中から選りすぐったキャッチコピーの方が、売れる言葉の可能性が高いですよね。
単語レベルでも構いません。切り口だけでも構いません。この段階ではとにかく数を書くことに集中します。アイデアを吐き出していくような感じで書きまくります。
ぼくはですね、マインドマップを使って書いたり、5W1Hを使ったりして切り口のアイデアを出していきますね。
いいキャッチコピーをたくさんの候補から選ぶ
100本書いたキャッチコピーの中から、いいキャッチコピーを「ひとつだけ」選んでください。
難しいですよね。
急にそんなこと言われても、どのキャッチコピーがいいかなんてわからないですよね。
書いたあとに出てくる問題が「キャッチコピーを選ぶ」という問題なんです。
そうなんです。「いいキャッチコピーの基準・定義」が自分の中にないと、キャチコピーは選ぶことができないんです。
では、いいキャッチコピーの条件はなんでしょうか
そう、課題解決でした。そして「人が動く言葉かどうか」が大事になってくるんですね。
人が動くとはどういうことかというと、
- 人の心を動かす(喜怒哀楽などの感情を変化させる)
- 人の頭を動かす(脳に記憶させる)
- 人の体を動かす(購入などの行動を促す)
これらの人が動く要因として、課題解決・つまり新しい発見や共感・気づき・納得が含まれていると考えて、キャッチコピーを選んでいくんですね。
この「いいキャッチコピーの基準」を作るために、コピーライターはいろんな作品を見て研究するんです。プロのコピーライターは書くプロであり、選ぶプロでもあるわけですね。
キャッチコピーを磨いて仕上げる
選び抜いたキャッチコピーは、さらに磨きをかけていきます。
具体的には、言葉の表現を変えたり、比喩や日常会話を意識したりして、お客さんに伝わるキャッチコピーに仕上げていくのです。
- 話し言葉にしてみる
- 漢字・ひらがな・カタカナにしてみる
- 逆説的な言い方にしてみる
- 主観的 / 客観的視点で言葉を変える
- 類語を探す
- 「てにをは」の省略
- 改行、句読点の位置を変える
- 倒置法で表現する
- 比喩表現を使う
レトリックを使ったり駄洒落を使ったり、なんでもありです。あらゆる方法で言葉を磨いていきます。
ぼくは大喜利を使ったりもします。
キャッチコピーの名作を知りたいかたは、こうしたキャッチコピー名作をまとめた本があるので参考にしてくださいね。
ここまでをまとめると、
まず、課題解決が含まれていることが重要でした。その上で、
- 何を言うか(What to say)
- どう言うか(How to say)
- キャッチコピーを書く
- キャッチコピーを選ぶ
- キャッチコピーを磨く
- 人の心を動かす(喜怒哀楽などの感情を変化させる)
- 人の頭を動かす(脳に記憶させる)
- 人の体を動かす(購入などの行動を促す)
- 共感がある
- 驚きや発見・気づきがある
- 納得できて・モヤモヤがスッキリする
プロのコピーライターもこのような工程でキャッチコピーを書いています。
キャッチコピーの考え方・ポイントとかテクニックとか
さて、ここからはキャッチコピーを考える上で意識した方がいいことだったり、細かいテクニックだったりを紹介していきたいと思います。
ゴール(目的)を意識する
商品を売りたいのか。認知を広げたいのか。ブランドイメージを伝えたいのか。
キャッチコピーの目的をきちんと意識することが大事なんですね。具体的には次のようなことです。
- 商品・サービスの売上向上
- 商品・サービス認知向上
- ホームページからの問い合わせ件数増加
- ホームページのPV増加(ページビュー Webサイトの閲覧数)
- SNSなどの拡散・口コミ
- ブランディングのためのキャッチコピー
- 社内のインナーブランディング
キャッチコピーや広告で、具体的に「何を」「どのくらい」達成したら成功と言えるのか。数値化できる目標・ゴール設定があると、のちにABテストや効果測定も可能になります。
キャッチコピーの掲載場所を想定しよう
考えたキャッチコピーは、どこに掲載されますか?
あらかじめ、掲載場所を確認しておくことも大事です。
- TVCM
- ラジオCM
- 新聞広告
- 電車つり革広告
- 街角ディスプレイ広告
- Web広告
- ランディングページ
- SNS広告
掲載する場所によって表現を変えたり、キャッチコピーを使い分けることもありますからね。
キャッチコピーは短く書こう
基本的に広告は見てもらえない・読んでもらえないと思った方がいいです。なので、できるだけ短く書くことを意識しましょう。
たとえば、テレビのCMを見ますか?
YouTubeの広告を最後まで見ますか?
キャッチコピーも例外ではないんですね。
キャッチコピーは「11文字から15文字前後」の言葉で考えたほうがいいと言われています。短く書くと次のような利点があります。
- 意味が理解しやすい
- 伝えたいことがひとつに絞られる
- 記憶に残りやすい
- 拡散しやすい
キャッチコピーは読まれてナンボですので、長くなり過ぎないように注意しましょうね。
キャッチコピーにはいくつかの種類がある
キャッチコピーとひとくちに言っても、実はいくつかの種類があります。
ちなみにこの記事で解説しているのは「イメージコピー」です。商品からイメージ・連想される言葉を表現するキャチコピーです。グラフィック表現や写真・映像も一緒に掲載・使用されることがほとんどですね。
他のコピーライティングの種類として、
商品やサービスの認知・販売という本質的な目的はいっしょなんですが、掲載場所に応じて使い分けたりします。
マーケティングの知識を利用した切り口の考え方
「キャッチコピーのアイデアと切り口、そんなに思いつかない」
ならば、マーケティングのフレームワークを知っておくと視点が増えますよ!
商品・サービスのベネフィット・切り口を考えていく上で、マーケティングの知識やフレームワークが役に立つんです。
商品・サービスを徹底的に取材する
商品・サービスの良さを伝えるためにはまず、その広告対象を徹底的に取材した方がいいですね。具体的には以下のようなことを行います。
- クライアントへヒアリング(オリエンテーション)
- 現場に行って取材する
- 商品・サービスを実際に使って体験する
- 書籍・インターネットなどで情報を調べる
- SNS検索(X (エックス)検索、Instagram検索)
- 実際に商品・サービスを使っている人に話を聞く
商品・サービスを利用し体験すること・実際に現場に行き自分の目で確かめることが大切ですね。
自分の感想や心の動き・発見をメモしておきましょう。それらのメモからキャッチコピーが生まれることがほとんどですから。
5W1Hで商品が生まれたストーリーを考える
その商品がどうやって生まれてきたのか。どんな人のどんな悩みを解決する商品なのか。
「5W1H」を使って文脈から考えていくと、より商品に対する理解が深まっていきます。
マインドマップを使って言葉を連想していく
マインドマップを使って言葉を連想していくと、思いがけないアイデアに巡り合ったりします。情報整理にも使えるので活用するといいですよ。
AIDMA(アイドマ)・AISAS(アイサス)で生活者の行動を想像する
AIDMA(アイドマ)・AISAS(アイサス)は、生活者・消費者が商品・サービスを購入するまでの思考を体系化したマーケティングの考え方です。
- Attention(存在を知り)
- Interest(興味を持つ)
- Desire(欲しいと思う)
- Memory(記憶する)
- Action(購入する)
AISAS(アイサス)は、Share(意見共有する・レビュー・口コミ・SNS拡散)が追加されたものですね。
キャッチコピーを考えるとき、商品と生活者との接点が現在どの段階にあるかを考える必要があります。商品認知の段階・商品購入の直前では、伝える切り口が変わってくるからです。
ターゲティング・ペルソナを決めよう
伝えたい相手は誰ですか?
誰に買って欲しい商品ですか?
年代・性別・業界などの分類をします。このことをターゲティングといいます。想定した人物像を設定します。
- 性別
- 年代
- 業界
- 既婚 / 未婚
さらに具体的に人物像を細かく設定していきます。このことをペルソナといいます。
- 名前(イメージ写真含め)
- 趣味
- 価値観
- パーソナリティー
- 職業
- 年収
ターゲット・ペルソナに合わせた言葉選びなどが、言葉の表現に影響してくるんですね。
カスタマージャーニーマップを作る
生活者・消費者が、商品・サービスを購買するまでの「感情」「思考」「行動」のプロセスを図示化したものをカスタマージャーニーマップといいます。
- どの時間帯に
- どんな環境で
- 誰と一緒にいるときに
- どんな気分で
生活者・消費者の生活を考え、広告対象である商品・サービスとの接点を探ります。
3C分析で広告対象の情報整理をする
商品・サービスの訴求点を明確にするためには、3C分析を使うといいですよ。
- 市場・顧客(Customer)
- 自社(Company)
- 競合(Competitor)
市場では今、何が求められているのかを把握しておくことも大切ですね。
4P分析で流通をイメージする
4P分析(マーケティングミックス)は、商品・サービスのプロダクトを4つの視点から分析するフレームワークです。
- 製品(Product プロダクト)
- 価格(Price プライス)
- 流通(Place プレイス)
- 販売促進(Promotion プロモーション)
その製品は「価値やメリットは何か」「どこで手に入るのか」「価格はいくらなのか」「広告はどこに掲載されるのか」など、把握することに適しています。
キャッチコピーのトレーニング方法
簡単にキャッチコピーを書けるようになればいいんですけど、そんな簡単に書けるようにはならないんですね。
そこで、ぼくがやっているコピーライティングのトレーニング方法を紹介しますね。
大喜利の考え方を利用する
キャッチコピーって、ちょっと大喜利に近いと思うんです。
とくにイメージコピーは発想力やアイデアが重要になってくるんです。新しい発見や今まで気づかなかった視点を探すには、ちょっと頭を柔らかくして考えていかなくてはいけなんですね。
- 〇〇〇は、〇〇〇だ!
- こんな〇〇〇は嫌だ!
- 〇〇〇の目線で言えば
こんな感じで、大喜利しながら考えることも必要だと思っています。
SNSで短い言葉で伝える訓練をする
SNSは文字数制限があるので、伝えたいことを端的に書く必要がありますよね。
キャッチコピー練習にはもってこいのツールなんですよ。フォロワーからの「いいね」「フォロー」などの反応がもらえる点も、効果を知る上で便利ですね。
X(エックス)を利用しているコピーライターも多いので、情報収集もできます。
公募でキャッチコピーの実績を作る
キャッチコピーの公募で「宣伝会議賞」という公募があります。
宣伝会議賞は日本最大のキャッチコピー公募で、コピーライターの登竜門と言われています。
プロのコピーライターも参加しているので、腕試しにはもってこいですし、実績を引っさげて広告代理店に転職するのもありかもしれませね。
公募を探したい方はこちらの記事をどうぞ!
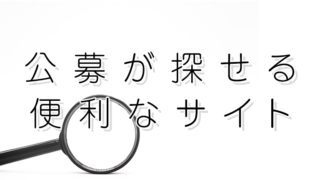
エッセイやコラム・ブログを書いてみる
キャッチコピーに限らず、コラムやエッセイなどのちょっと長めの文章を書くこともいいトレーングになりますね。
コピーライティングでは、キャッチコピーだけでなく、キャッチコピーのあとに続く長い文章、リードコピーだったりボディコピーだったりも書く必要があるからです。
体験談やエピソードを語れるようになると、説得力のあるセールスコピーが書けるようになります。
個人ブログなどで、コラムを書いたりするのもいいですね。アクセス解析などの効果測定は、コピーライターとしては重要な視点になりますしね。
ぼくはnoteでエッセイを書いています。
クラウドソーシングの案件に応募してみる
練習ばかりしていても、本当の実力はついてきません。
実践を積みたいのなら、クラウドソーシングの案件に応募してみるのもいいと思います。
クラウドワークスやココナラなどのクラウドソーシングサイトで、キャッチコピーやWebライティングの案件を探してみましょう。
個人事業主としてもフリーランスとしても、副業など、仕事の幅が広がっていきますよ。
キャッチコピーは個人事業主・フリーランスの最強の武器になる
いい商品だとしても、その存在が知られてなかったり、魅力がうまく伝わってなかったりして売れていないものは世の中にたくさんあると思います。
キャチコピーは物事のいい部分にスポットライトを当てて、価値を再定義することだと思うんですね。
たとえば自分で商品を作った時、商品の価値は自分で伝えたくなるじゃないですか。その商品の良さは、自分がいちばん知っているわけですから。
これからの時代、個人事業主やフリーランスの方は自分でアピールする方法を身につけていかなくてはいけないと思うんですよ。
フリーランスの人は、自分自身をクライアントに提案していかなくてはいけないですね。
そんなとき、このキャッチコピーの考え方がとても重要なスキルになってくると思うんですよね。
ぜひ、このブログを活用して、キャッチコピーコツを掴んでいってください。
他にもキャッチコピーに関する記事をたくさん書いています。
最後まで読んで頂いて、ありがとうございました。