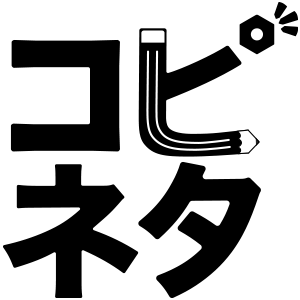相手に伝わる文章の構成と完読される書き方とは
時間をかけて書いた文章が相手に伝わらない。
最後まで読んでもらえなくて、相手の理解が甘い。
そんな経験ばかりが続いてしまうと、文章を書くことが億劫になりますよね。
伝わらない文章を書き続けることで、あなたの仕事は増えてしまうかもしれません。
そうなる前に、文章について考えてみませんか?
こんにちは、のざき寿(ひさし)といいます。元芸人です。
当サイトに来てくださり、ありがとうございます!ゆっくり見ていってくださいね!
文章が伝わらない最大の原因は、なんだと思いますか?
それは、文章の構成です。
要するに、伝える順番が重要だということです。相手に内容をつたえるのに、文法のテクニックや美しい比喩表現を覚える必要はありません。
- 何を
- どの順番で伝えて
- どうして欲しいか
文章の構成の方法として、三幕構成をご紹介します。三幕構成とは、文章全体を「序章」「本論」「まとめ」と3つのパートに区切って構成する考え方です。
では、文章の構成について考えていきましょう。
なぜ、結論から書けと言われるのか
たとえば、会社の上司に「結論から先に話せ」と言われたことはないですか。
報告の場面、会議の場面など、まずは結論を先に伝えることが大切です。それは文章の構成でもまったく同じことがいえます。
ゴールを先に示してから文章を書く
結論を語らないまま文章を構成してしまうと、読み手は文章を読み進めていった先に、自分の求めている情報が書いてあるか不安になります。
つまり、ゴールが見えないままマラソンを走っていることになるわけです。
最後まで文章を読んだにも関わらず、求めていた結論がなかった場合を想像してみてください。
疲れてしまいますよね。なので、結論から書く必要があるわけです。
結論を決めると文章の構成は簡単になる
結論さえ先に書いてしまえば、文章の構成は簡単になります。
後々になって「伝えたいこと・言いたいことはなんだったか?」そんな状況に陥ることがなくなります。
結論から構成してその後に根拠や理由を書く
結論となるゴールを先に語るようにして、そのあとにゴールまでの道筋となる理由や根拠、データや感想などを構成していきましょう。
とくにWebライティング・ブログなどで書かれるインターネット上の記事は、
これは、報告や論理的な文章の書き方や構成のテクニックです。
小説やエッセイ・コラムといった読み物は、ゴール・いわゆるオチを先に伝えてしまうと面白さが台無しになってしまうので、結末は最後まで書かないようにします。
文章の結論とは読み手にとって有益なこと
結論で語ることは、読み手にとってメリットになることを書きましょう。
とくにブログなどの記事は、検索してきた人に向けて解決策を早めに提示する必要があります。結論が上部にないと離脱の原因やスクロールされて読み飛ばされてしまいます。
読み手にとって嬉しい未来を先に語るようにしてください。読み手にゴールイメージを持ってもらうことが大切です。
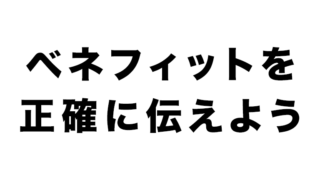
完読される文章の三幕構成とは
ここからは、もう少し突っ込んだ文章の構成について考えていこうと思います。
文章は三幕構成で書くと読みやすい文章になります。
三幕構成とは、文章の構成を三幕「序論」「本題」「まとめ」の3つのパートに分けて構成する文章のテンプレート、いわゆる文章の型です。文章を論理的に書くことに向いている構成です。
序論の書き方
文章の導入部分です。文章全体の2割くらいの文章量で構成します。
文章の冒頭では、結論となる文章のゴールを読み手に語りましょう。そのあと結論に至った理由などを述べていくと、読み手に内容が伝わりやすい文章になっていきます。
本論の書き方
文章全体の核となる部分です。文章全体の6割くらいの文章量で構成します。
具体的なエピソードやデータ、根拠・理由などを丁寧に解説し、序論で語った結論の裏付けをしていきましょう。
まとめの書き方
文章の総まとめを書きます。文章全体の2割くらいの文章量で構成します。
読み手に対して、とくに印象づけたい主張や想い・行動の提案などを書きます。
文章の三幕構成は「2:6:2」
実はこの三幕構成、アメリカの脚本家「シド・フィールド」によって論理化された映画の手法です。ぼくは文章構成にも応用できると思い、論理的な文章を書くときに使用しています。
三幕構成についてもっと深く知りたい方は、こちらの脚本術をお勧めします。ヒットする映画の構成について解説している本です。
文章は段落(パラグラフ)が積み重なって構成されている
さらに文章の見出しと段落について考えていきましょう。
文章は段落が積み重なって、ひとつの文章になります。段落のはじめには見出しがあり、その後に文節が積み重なって構成されています。
段落は見出しから書く
段落のはじめは、見出しから書きます。見出しはこれから書く文章の概要を短いことばで端的に表現します。
魅力的な見出しを書くことは、そのあとに続く文章への興味に繋がります。
キャッチコピーの考え方を参考にするといいですよ。見出しは文章の完読にはとても重要な要素です。
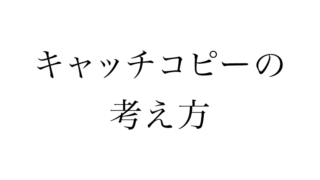
段落の書き方
ひとつの段落につき、4〜8文が適切でしょう。それ以上の段落になると情報量が多くなりすぎてしまい、伝えるたいことがぼやけてしまいます。改行をするなどして、文節を区切って書きましょう。
最初の段落では要約を書く
見出しの次にある最初の段落には、結論となる要約を書きましょう。
段落にも三幕構成である、序論・本論・まとめの書き方を当てはめていきます。つまり、段落も結論からはじめ、そのあとに根拠や理由、データを書くようにしていきます。
読み手に負担を与えない文章を書こう
このように各章・各段落で構成を決めておくと文章の構成で悩むことが少なくなり、内容に注力できるようになります。そして、パターン化すると読み手にとっても読みやすい文章になっていきます。
読み手に負担を与えないことが、文章を最後まで読んでもらうためには大切な考え方になります。
文章の導入部分はとくに重要
文章の書き出しには、とくに力をいれて書きましょう。読み手はいつでも文章を読み進めないという選択肢を持っているため、文章の導入で読み手の興味・関心を惹けない場合、最後まで読んでもらえなくなります。
セールスライティングは、読み手の感情の起伏を意図的に作り、関心を惹きつけて商品やサービスを訴求していくライティングのテクニックです。以下の記事で詳しく解説していますので、参考にしてみてください。
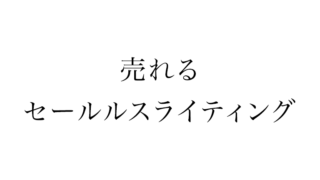
文章を見直す時に注意したいこと
三幕構成の型に沿って文章を書き上げたら、文章全体を見直す作業をします。
自分の伝えたいテーマと読者が知りたいことが一貫性をもって語られているかを確認していきます。
言い回しや誤字・脱字、文末表現などは、文章の構成を見直した後に行ないましょう。綺麗な文章が書けていたとしても、伝わらない・最後まで読まれない文章では意味がありません。
読者に伝えたいタイトルやテーマが絞り込まれているか
文章のタイトルと本文の内容に、ズレがないかを確認しましょう。
読み手は、タイトルから得られるベネフィットを期待して記事を読み進めていきます。タイトルと内容が一致していない文章は、読み手は不要と感じ、読み飛ばしや離脱につながってしまいます。
文章を書き進めていると、あれもこれもと詰め込みたくなります。ブログであれば文字数を稼ぐために書かなくていい文章を書いてしまうことがあります。テーマに関係ない冗長的な文章は、読み手にとって負担でしかありません。
タイトルとテーマの関連性を意識して、文章をチェックしていきましょう。
読者に向けた文章になっているか
執筆に没頭するあまり自分の世界に入り込んでしまうことがあります。つまり読み手を無視した文章になってしまうことがあります。
文章を見直すときは、読み手が今・どんな気持ちでこの文章を読んでいるかを想像しながら、読み手との距離が離なさないように書かれている文章か、確認しましょう。
1次情報や個人の視点や切り口があるか
文章は、経験談やエピソード、独自の主張・分析が大切です。このことを1次情報といいます。
勉強中の知識などは、調べた情報の再編集であり2次情報です。情報としての価値は低くなります。自分の考えや切り口・視点を交えて文章を構成することが大切になってきます。
何を書かないかを考える
書くことを決めるよりも書かないことを決めることが、文章をよりスマートにしてくれます。情報を集め取材した期間や努力が大きければ大きいほど、ひとつの記事詰め込みたくなる気持ちはわかります。ですが読み手は、悩みや課題を解決する手段を求めているので、必要以上の情報はいらないのです。
書かないことを決めることで逆に、書きたいこと・書かなくてはいけないことが明確になっていきます。
ブログ記事は3,000〜5,000文字を目安に構成する
ブログ記事の文章量は、長すぎても少なすぎてもいけません。長すぎれば情報過多になり読み手が疲れてしまいます。逆に少なすぎる文章量の場合は、あえて記事にする必要性はないのかもしれません。
ブログ記事は、3,000〜5,000文字の目安に書くといいでしょう。このくらいの文章量でまとめると、ひと記事でひとつのテーマを扱うことができ、三幕構成で文章が構成しやすくなります。
適切な文章量は、章全体を通して大見見出しや小見出しを適切に配置していくことになります。読み手にも読みやすい文章になり、SEO(検索エンジン最適化)にも効果があるとかんじています。
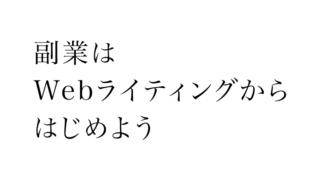
何度も構成を見直して文章を磨いていこう
書き終わった文章はそこで終わりではなく、推敲のスタート地点に立ったと考えましょう。
たとえばブログ記事のいいところは、自分のタイミングで何度でも書き直せることです。追加したい体験談やアイデア、事実確認などがあればいつでも修正ができます。書き直しが利かない新聞や雑誌などと違う有利な点があります。
またブログに関していえば、アクセス解析などを導入することで分析か可能になります。読み手の行動をイメージして文章の手直しができる点で、効果を出しやすく文章の学習にも最適だと感じています。
文章を書く目的は、人の感情を動かし行動させることです。そしてあなた自身の成長を図っていってくださいね。