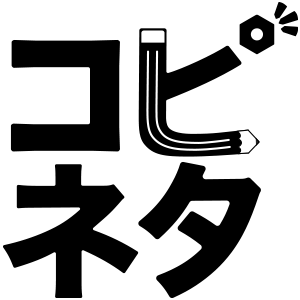マインドマップ初心者が知っておきたい書き方と使い方とは
「いろいろ考えすぎて、頭がパンクしそう」
もしあなたが頭を抱えて悩んでいるなら、だまされたと思ってマインドマップを使ってみてください。
たとえばマインドマップはこんなときに役に立ちます。
- 新しいことを学び始めたとき
- 新しい職場で早く仕事を覚えなくてはいけないとき
- 読んだ本の内容を効率よく記憶したいとき
とにかく多くの情報を整理したいとき。マインドマップはアンパンマンくらい心強い味方になってくれます。
こんにちは、のざき寿(ひさし)といいます。元芸人です。
ぼくは文章の構成を考えるときやアイデアを考えるときにも使っています。
マインドマップを使い始めたあなたに、書き方と使い方・気をつけたいポイントをご紹介できればと思います。
マインドマップはあなたの脳内そのもの
とつぜんすみません。この記事でいちばん伝えたいことなので最初に話させてください。
マインドマップはあなたの脳内の思考を主観から切り離すツールです。
あなたの脳内の思考は、頭で考えているうちは目に見えない主観の状態です。マインドマップに書き出すことで思考は脳内の外に出されます。
つまり脳内の思考は、主観から切り離された瞬間に客観的に変化するのです。
思考が客観的になると何がいいのでしょうか。
思考を客観的みつめることで、分析や原因の追求・解決策の検討ができるようになるわけです。
悩みごとをマインドマップで書き出してみよう
悩みごとって、頭の中でグルグルとメリーゴーランドのように回りますよね。しだいに雪だるまのようにどんどん大きくなってしまいます。
そんなときは、いったん悩みごとをマインドマップで書き出してみましょう。
すると悩みごとは、あなたの脳内から切り離されます。脳内から悩みごとを取り出してしまいましょう。
もう、あなたの悩みごとは他人事です。あとはゆっくり解決策を考えていけばいいのです。
ぼくは悩みごとのほかにも、不安に思っていること・怒りに感じていることなど、自分の感情もマインドマップで書き出すようにしています。書くという行為で冷静にもなれますしね。
マインドマップ初心者がおぼえておきたい3つの用語とは
マインドマップの書き方を解説したいところです。が、マインドマップ特有の用語があるので、さっと紹介しますね。
おぼえておきたい用語は次の3つです。
- セントラルイメージ
- メインブランチ
- ブランチ
「セントラルイメージ」はマインドマップのテーマです
マインドマップの中央に描くテーマ(主題)をセントラルイメージといいます。テーマを中央に配置する「放射型」と、テーマを右に配置する「右マップ型」があります。
放射型のマインドマップは発想を自由に展開することに向いていて、右マップ型のマインドマップはテーマを掘り下げていく時に向いています。
ちなみにセントラルイメージは、イラストで描いても問題なしです。
「メインブランチ」は太い線のこと
セントラルイメージから伸びる太い線のことをメインブランチといいます。カテゴリーごとに色を変えたり、優先度・重要度によって色を使い分けたりします。
マインドマップは、色をつかってカラフルにしていいのです。
「ブランチ」は要素を関連付けるための線
ブランチは「枝」を意味しています。マインドマップは、樹齢何十年の木が育つイメージで、セントラルイメージからメインブランチへとつながり、そしてブランチへと広がっていくように描いていきます。
ブランチの数は、脳内の情報量や発想と比例しています。
脳の取扱説明書としてマインドマップは開発されました
ここで少しだけうんちくになります。
せっかくなのでマインドマップが生まれた背景も解説させてくださいね。
マインドマップは、もともと学習能力の向上が目的で開発されました。
脳内に近い形で描き出すことで、記憶の整理や発想を手助けする「脳の取扱説明書」だったのです。
1970年、イギリスの教育コンサルタントの「トニー・ブザン氏」が提唱しました。
トニー・ブザンは、学習に困難を抱えていた子どもたちにマインドマップを教えた。マインドマップの効果で子どもたちの学習能力を大きく向上させたことが、イギリスの公共放送BBCで報じられ世界で広く知られるようになった。
Wikipedia
マインドマップの書き方と箇条の書き方の違い
マインドマップと同じような情報整理の方法に、箇条書きがあります。
決定的な違いがあって、マインドマップは情報の構造化・階層化をするのに対し、箇条書きは情報を並列でならべていきます。
箇条書きの特徴とは
ひとつひとつの項目に対し優先度や重要度・カテゴライズはしません。思いついた順に書いていきます。簡易的なメモやチェックリストに向いていますね。
マインドマップの特徴とは
テーマ(主題)から連想される単語を連結させて書いていきます。マインドマップは、単語ひとつ一つの関連性を意識して書く必要があります。
また優先度や重要度の高い項目は、色を変えたりイラストを加えたりして強調します。ビジュアライズして脳の情報を映像として書き出し、記憶の定着をうながすのです。
マインドマップ初心者のための書き方とは
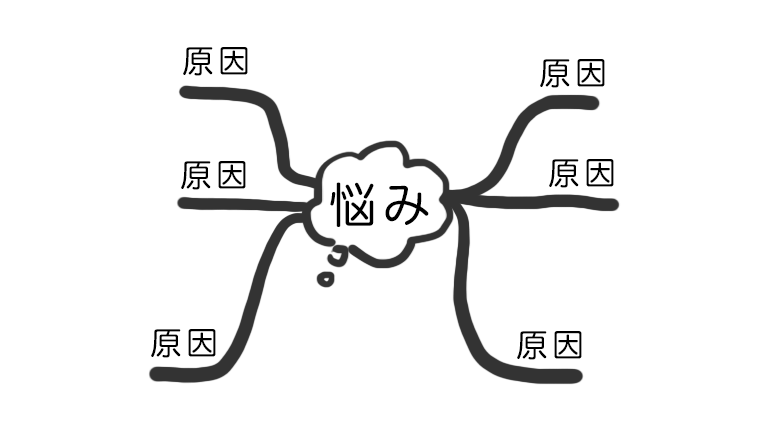
それではマインドマップの書き方についてはじめましょう。おしながきは、つぎの内容です。
- A3、A4の無地の用紙を使う
- セントラルイメージはイラストで描いてもいい
- メインブランチの線は太くする
- ブランチはひとつの言葉で書く
- ブランチは色を使って描く
- 構造化を意識した書き方をする
初心者ほど基本的な書き方を意識したほうがいいです。
マインドマップには「A3・A4無地」の用紙を使う
用紙の大きさが、思考の広がりを決めるといわれています。
大きすぎず小さすぎないサイズが、A3用紙・A4用紙じゃないでしょうか。大きいわら半紙にポストイットを貼っていくのも面白いですね。とにかく小さすぎないことです。用紙は横向きでつかいましょう。
ノートなどの罫線のある用紙ではなく、無地のコピー用紙のほうがいいです。
罫線のある用紙だと言葉を整列させて書きたい意識が働いて、マインドマップの自由度が低くなってしまします。自由な発想を大切にするマインドマップでは、罫線が邪魔になってしまうのです。
セントラルイメージはイラストで描いてもいい
セントラルイメージは言葉で書いてもいいですが、イラストで描く・イラストを加えることをオススメします。
イラストは視覚情報です。人間は情報を、視覚と聴覚だけで93%認識するといわれています。それに対し言語情報はたったの7%しかありません。つまり画像は文字の7倍、情報を伝達するのです。
マインドマップの真ん中にドンッ!とイラストがあるほうが、だれが見てもテーマがわかりやすいですよね。イラストがあると情報の共有がしやすくなるわけです。
メインブランチの線は太く・曲線で書く
メインブランチは太い曲線にしましょう。
太い線は、重要度や優先度を表現しています。
曲線は、思考の柔軟さを引き出す効果があります。直線では表現できない、感情やこころの機微を表現できます。
ブランチはひとつの言葉・意味で書く
ひとつのブランチはひとつの単語・ことば、ひとつの意味で完結するように書きます。
ブランチを文節や文章で書いてしまうと、ひとつのブランチが持つ意味が複雑化してしまい構造化できなくなっていきます。発想や思考の見落としにも繋がってしまうのです。
ひとつ例を挙げると。
「水を飲む」ではなく、
「水」でひとつのブランチ「飲む」でひとつのブランチとします。
水に関する行動は「浴びる」「買う」など、複数の行動が考えられるからです。
これはよくやってしまうので注意が必要です。
ブランチは色を使って描く
ブランチの線に色をつけることで意味を持たせることができます。これもイラストとおなじく、相手に意味を伝えるときに便利ですよ。
- 赤:緊急性が高い
- 青:検討事項
- 黄色:アイデア
マインドマップはカラフルにすると描いていてたのしいですよ。
構造化を意識した書き方をする
ブランチに階層やカテゴリーを持たせて構造化しましょう。これがマインドマップの書き方で最大の特徴です。
構造化は思考の深さを表現しています。また全体像が把握しやすくなり、客観的・俯瞰的な視点がうまれ、思考を観察できるようにもなります。
まだ発見できていないアイデアや連想を、マインドマップで見つけてくださいね。
具体例からマインドマップの書き方を学ぼう
マインドマップは、仕事からプライベートまで幅広く使うことができます。
情報整理や学習はもちろん、先にお伝えした悩みごとの解決・発想やアイデアを考えるときなど、あなたのアイデア次第で無限の可能性を秘めています。
ビジネスの場面で使えるマインドマップの書き方
企画会議や商品開発、競合調査・議事録の作成。
あらゆる仕事の場面でマインドマップは活躍してくれます。
とくに企画会議などのブレインストーミングでは、そのポテンシャルを存分に実感できるでしょう。
企画会議・ブレインストーミングの書き方
セントラルイメージにテーマから連想できる単語を思いつくかぎり書いていきます。
とにかく頭の中にある言葉を吐き出していくことが、企画やブレインストーミングととても相性がいいのです。
思いがけない発想に出会うことができます。複数人で会議をしていて、アイデアが枯渇したときに使うのもいいですね。
ブレインストーミングでマインドマップを使うと、構造化によって発想の出発点が明確になるので、のちに論理的な説明もしやすくなります。
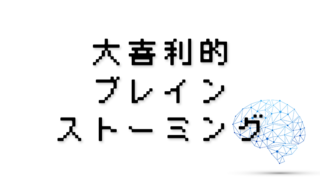
議事録の書き方
会議のテーマを真ん中におき、アジェンダをメインブランチに配置しておきます。
アジェンダごとに議事録を記録していけば、会話の出どころが明確になり「そもそも論」や「水かけ論」の軌道修正ができます。
マインドマップの議事録は、見た目にも分かりやすいのでそのまま共有できます。
情報整理・分析の書き方
競合分析や商品の調査などにマインドマップを使います。
- 対象(テーマ)の、何を知っているか
- 対象(テーマ)の、何を知らないか
知っていること・知らないことが分かれば、分析のヌケ・モレが少なくものごとを掘り下げられます。
ぼくはキャッチコピーを考えるときに、マインドマップを使っています。
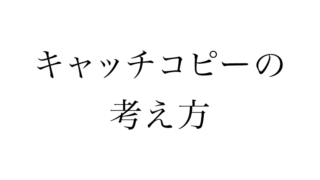
プライベートの場面で使えるマインドマップの書き方
新しく何かを学び始めるとき、旅行のために準備するものをメモしたいときなど、マインドマップはアイデア次第でいろんな使い方ができます。
資格取得の学習でマインドマップを使う
参考書の目次を参照して、各章ごとにマインドマップを描いていきます。
学んだ用語や内容をどんどんブランチにしていきます。すると資格取得のために学ぶ必要がある項目が構造化でき、全体像がわかりやすくなります。
また、関連し合うブランチは理解や記憶の手助けをしてくれるのです。視覚情報としてイラスト化することも記憶の定着にひと役かいます。
さらに得意な分野・苦手な分野の認識もできるので、弱いところを効率よく重点的に学習すればいいのです。
履歴書・職務経歴書の作成にマインドマップを使う
あなた自身をセントラルイメージにします。
自分を客観視して、得意なこと・不得意なこと、技術や経験などをブランチにしていきます。職歴・資格などもブランチにします。履歴書の枠では見つからない、自分らしさを見つけることができますよ。
一方で、応募する会社に対してもマインドマップを作ります。その会社の特徴を分析していきます。
自己分析と企業分析の交わるところを積極的にアピールしていきましょう。
目標達成・課題解決にマインドマップを使う
目的や目標・成果や結果をセントラルイメージにします。
目的や目標を達成するための手段をブランチにして描いていきます。結果から逆算して手段をさぐっていきましょう。

他者とのコミュニケーションにマインドマップを使う
マインドマップは相手との情報共有にとても便利です。
文字情報よりも直感的にイメージが伝わります。視覚的な情報伝達になるわけです。つまり、見れば誰でもわかるのです。
ブランチに色を使ったり・線の太さや形状・長さを工夫したりして、一枚の絵のように仕上げていきましょう。
マインドマップ上級者の書き方とは
慣れてくると基本を忘れてしまうのはどんなことでも一緒です。
マインドマップを描き慣れたときに注意したいことをいくつか紹介しますね。
初心者も上級者もマインドマップは手書きで描く
手書きで描くと脳が刺激されます。脳への刺激よってアイデアが浮かびやすくなります。
マインドマップをインターネット上で作成できるサービスはたくさんありますが、できるだけ手書きのほうがいいでしょう。画像よりも手書きにイラストの方が、そのひとの個性がでて面白いです。
手書きで書いたのちに、デジタルツールで保存するのもいいですね
TEFCAS思考法取り入れたマインドマップの書き方
マインドマップの考案者、トニー・ブザン氏が提唱する「TEFCAS思考法」をマインドマップに取り入れてみましょう。
TEFCAS思考法は、新規事業・アイデア実現のための思考法で、次の単語の頭文字を取って「TEFCAS」となります。
- T (Trial):試行
- E (Event):実行
- F (Feedback):フィードバック
- C (Check):チェック
- A (Adjust):調整
- S (Success):成功
達成したい目標をセントラルイメージにし「Trial(試行)」する項目をメインブランチにしていきます。「Success(成功・成果)」を意識して、ほかの項目をブランチにして構造化していきます。
悩みを解決してアイデアに溢れた毎日を
僕がマンドマップをいちばん使っているときは、悩みや不安がある時です。
主観でものごとを考えていると、独りよがりの考え方になって解決策の糸口が見つからないことが多いです。そんなときはすかさずマインドマップ描いて、自分の思考から悩みや不安を切り離します。
客観的になると「ああ、こんなことで悩んでいたのか」と、冷静な判断ができ頭がクリアになるのです。脳のスペースが空いたような気分になります。
もんもんとアイデアを考える時にもマインドマップを使うし、このブログ記事の構成を考えるときに真っ先にやる作業が、マインドマップで情報を整理することなのです。
ノートとペンさえあればいい。とてもお手軽ですよね。
マインドマップはあなたの脳内です。それは自分と向き合うことにほかならないでしょう。