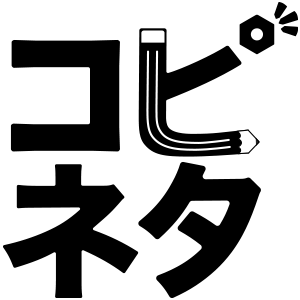エッセイストになるには?文章を書いて収入を得る

あなたはなぜ、エッセイストになりたいのですか?
ぼくは自分が体験した、楽しかったこと嬉しかったこと、辛かった想いや悔しかった感情文章で伝えて、
その想いで誰かひとりでもいいから心が動いて生活に彩りがでたらいいなと思って、
そんな想いで、エッセイを書いています。
自分の思ったことを感じたままに文章にして、読んだ人が共感してくれる。
そしてそれが収入につながり文章を書くことが仕事になる。
エッセイストを名乗った瞬間に、あなたもぼくもエッセイストです。
でも、エッセイストを名乗って文章を書こうと思っても、実際、
- エッセイをどこに書いていいかわからない
- 収入に繋げる方法がわからない
- 面白いエッセイを書く方法がしりたい
このような現実的な課題にぶつかると思います。
ぼくも同じように、これらの課題にぶつかってきました。
もし、芸能人やタレント・作家なら、執筆のオファーがあるかもしれませんし、私生活を曝け出す文章を書いただけでファンの人は読んでくれるかもしれません。
でも、ぼくは全くの無名です。
あなたは、無名の人のエッセイを読みますか?
エッセイストを諦めてしまうことは簡単ですが、ぼくはエッセイストになる方法をいろいろ探してみました。
そしてnoteと出会いました。
ぼくはnoteでエッセイを書いています。
noteは、文章を中心としたコンテンツプラットフォームです。SNSよりも長い文章で、日記や創作を発信するクリエイターが多く利用しています。
エッセイストを名乗って、2年前から毎日noteでエッセイを書き始めました。
今では、ぼくのエッセイをお金を払って読んでくれる方々がいます。
また、noteでエッセイを書きながらエッセイの公募に応募したら、賞をいただくことができました。
無名なら、有名になっていくために努力すればいいんだと思いました。
だからあなたにもチャンスはありますし可能性を持っているんです。
今ではnoteのフォロワーさんが1,000人を超えています。フォロワーさんがぼくの文章をお金を払って読んでくれています。
感謝ですねぇ。
文章を書き続けて実績を積み重ねていけば、エッセイストの道は開けていくということですね。
この記事では、
あなたがエッセイストとしての第一歩を踏み出せるように、ぼくの体験談をお話したいと思います。
エッセイストになるには何から始めればいいのか
とにかく、文章を書くこと。
書いた文章を発表することが大事だと思いました。
「文章力に自信がないから…いい文章が書けるようになるまで文章力を磨こう」
「いい作品に仕上がってから…作品を発表しよう」
そうして文章が上手くなるまで準備をしてると、どんどん書く手が止まっていってしまったんですね。
ぼくがエッセイを書いていて「どうしたら文章力が身に付くのか」を考えた時、いちばん思うのは、
- とにかく書くこと・書き続けること
- 自分以外の誰かに読んでもらうことを怖がってはいけない
ということでした。
いい文章・いい作品を評価するのは自分ではなく他人が評価します。まずはエッセイを書いて発表することが重要です。
だからぼくは、エッセイを書く場所を探しました。
noteでエッセイを書いています
ぼくはエッセイを発信する場所としてnote(ノート)を選択しました。
noteは文章に特化したコンテンツを発信できるサービスです。
エッセイストの方はもちろん、小説・コラム・論文・ビジネス文書など、文章に関するコンテンツを作っているクリエイターさんがたくさんいます。
ぼくはまず、noteで毎日エッセイを書くことから始めました。
そうそう、noteはアカウントを作るだけで無料で使えます!
テーマを絞ってエッセイを書くようにした
ぼくは「介護職員」「元お笑い芸人」という肩書きを名乗ってnoteを書いています。
ぼくはデイサービスで介護福祉士として働く介護職員です。
介護現場で起こった出来事や感じたことをテーマにエッセイを書いています。
テーマを絞らずにエッセイを書くと、読者の方に覚えてもらえないのではと思ったからです。
なのでnoteのアカウント名やプロフィールの文章は、一目で介護職員と分かるようなものにしています。
読者のためにエッセイのテーマを絞る
たとえば書店へ行ってみるとわかるのですが…ノンジャンルの本ってないですよね。
ぼくは本を買うとき、
自分の知らない世界を覗いてみたい…
専門的なことを知って、物事を深く理解したい…
こんなことを思って本を手に取ります。
わかりやすく、自分にラベルを貼っておくってことが大事なんですね。
「介護の世界を知りたい人はたくさんいるだろうなぁ」そう思ってテーマを考えました。
おのずとエッセイのコンセプトが決まってきますし、ターゲット(読者)も決まってきます。
有名作家や芸能人・タレントなら何を書いてもいいでしょう。それは「名前や顔でエッセイを売る」ことができるからです。
でもぼくは無名です。だからこそ読者の興味を惹くように、ひとつのテーマに絞ってエッセイを書いたほうがいいと思ったのです。
まずはエッセイを手に取ってもらうこと・読んでもらうことが大事だと思います。
note有料記事販売でエッセイストになろう
noteを使ういちばんの理由は、自身のエッセイに値段をつけて有料記事として販売できるからです。
エッセイは書いたら売れる、ということはありません。
値付けも自分でやらなくてはいけないし、エッセイの宣伝も自分でしなくてはいけません。執筆と編集者の役割を同時にやる必要があります。
noteはインターネット上のサービスなので、製本にかかる費用はありません。
また、無料でアカウントを作ることができるのでコストはゼロです。
あとから値段も変えられますし、期間限定でセールできたりします。加筆や修正もすぐにできます。
だからまず、noteでエッセイを売ることがエッセイストになるの近道と考えたんです。
「自分の書いたものに、いくらの値段がつくのか」
作品を書く楽しみも作品を売る楽しみも一緒に味わえます。
はじめてエッセイを買ってもらったとき…
人生で一番嬉しかったかもしれません…
作品を販売することが、書くモチベーションにもつながっています!
プロの作家でも有料記事を販売している人は多くいますし、芸能人もいますし文化人もいます。
エッセイを売るという商売の視点も、作家・エッセイストには大事なんです。
noteの使い方シンプルです。
難しい機能はなく、執筆に集中できるようにスマートな設計になっています。
個人のクリエイターが多いですが、企業がオウンドメディア(自社ブログ)としても活用していたりと、利用するユーザーはどんどん増えていいます。
まずはアカウントを作ってみましょう!
エッセイの存在に気づいてもらうための工夫
書いただけでは、エッセイを読んでもらえることはありませんでした。
どれだけ一生懸命書いたエッセイでも、見つけてもらえなければ伝わらないんですね。
そこでぼくは、エッセイを売ることよりもまず、
- エッセイを読んでもらうこと
- ぼくの存在を知ってもらうこと
このふたつを意識してnoteの運用をしました。
noteの無料記事で自分のファンをつくる
まず、ぼくのエッセイを読んで欲しい。
noteは基本的には無料で使えるサービスです。
ぼくはとにかく無料記事を毎日書きました。それこそ365日、毎日投稿を続けてフォロワーさんを増やして行ったんです。
「スキ」や「フォロワー」をたくさん増やしておけば、有料記事を販売したときにフォロワーさんがエッセイを買ってくれると思ったんですね。
noteのフォロワーさん500人を超えたときに
はじめて有料記事を販売してみました。
初めて販売したnoteの値段は「100円」です。
高いですか?安いですか?
文字数はだいたい1,200文字前後。原稿用紙にして3枚です。
たとえば、有名作家の文庫本は「500円」くらいしますよね。
無名のエッセイストの作品で1編のエッセイ。もしかしたら「100円」でも高いかもしれません。
結果は、
4人の方が買ってくれました!
はじめてエッセイで稼いだ金額は400円でした
たった400円…と思うかもしれません。なんならnoteに手数料支払うので、収益は300円くらいです。
でも、ぼくは飛び上がるくらい嬉しかったですね。
エッセイって、売れにくいんですよ。
文章の販売って、ノウハウや耳寄りな情報は実用的なので価値がわかりやすいです。
エッセイって生活や仕事の役に立つかと言われれば、そうではないですよね。
だからこそ、嬉しかったんです。その後のエッセイも買ってくださいました。
無料記事を書き続けていたおかげでエッセイを書く文章力も向上していました。そういった実感も確実にありました。
興味を惹くエッセイのタイトルを考える
noteには、ぼくの他にもエッセイを書くクリエイターさんがたくさんいます。
エッセイストを目指している方・文章で収入を得ようとしている方は、ぼくだけじゃないんですね。
競合ひしめくクリエイターの中で、ぼくの作品を選んでもらわなくてはいけません。
エッセイのタイトルを工夫しました。
タイトルに「検索キーワード」を入れる
noteは、タイトルに含まれているキーワードをもとに、お勧め記事を表示するシステムを採用いしてます。
たとえば、ぼくのエッセイであれば、
「介護」というキーワードを入れた場合と入れない場合では、明らかにエッセイのアクセスが違っていました。
これはSEO(検索エンジン対策)というシステムで、Google検索でも同じような仕組みを採用しています。
ぼくはWebライターとしても仕事をしているので、そういった検索システムに関して詳しいんですね。
自由にタイトルをつけられないこともありますが、読んで欲しいのはタイトルではなくエッセイなので、そうしてタイトルを考えていきました。
セールス・マーケティングの知識を学ぶ
ぼくはエッセイの他にも、実用的な内容の文章も販売しています。
たとえば「noteのコンセプトの作り方」「習慣化するために意識していること」など、ノウハウや知識に関することも書いています。
こうした文章のほうが売りやすいのですが、
それでも簡単には売れませんでした。
有料記事は、読者は購入しないと内容がわからないため、無料記事で読める部分でいかに商品の価値を伝えるかがポイントになってくるんですね。
そのためには、マーケティングやセールスの知識が必要になってきます。
- 誰に(ターゲット・ペルソナ)
- 何を(どんな価値・ベネフィット)
- どう伝えるか(切り口やアイデア)
記事を販売してみて、売ることの楽しさを知りました。
読者に価値をどのようにして伝えるかを考えることは楽しいです。
noteを売って収益を得たいなら、マーケティング・セールスの知識は必須だと思いました。
読者を想像してエッセイを書いた方がいいエッセイが書けます。
そのためには「読者は何を求めているか」を想像する必要があります。
マーケティングはお客さんを考えることです。
専門的で実践的な内容ですが「商品の価値」というものをとても分かりやすく解説してありますので、入門書として一押しの本です!
この本に関しては、もう何度読んだかわからないくらい読んでいます。
この記事に関しても、この本のセールスライティングを参考に書いているくらいです。
超オススメなので、ぜひ手に取って読んでみてください!
エックス・インスタグラムでエッセイを告知する
noteでエッセイを書いた時は、SNSでの発信もしています。
できるだけ多くの人にエッセイの存在を知ってもらいたいからです。
逆にSNSで有名な方は、エッセイは売りやすいかもしれませんね。
noteには簡単いSNS共有ができる機能が搭載されていますので、使い勝手もいいんです。
売れるエッセイストになるために公募で賞を取る
思うようにエッセイが売れない…
売れることを想像して、ワクワクドキドキしながら処女作を発表して…
noteでエッセイを販売してみたものの…
全く売れない…確実にこの壁にぶち当たります。
ぼくの書いたエッセイも、たくさん売れるってことは、まだないです
でも、あることをキッカケにポツポツと買ってくれる人が現れました。
そのキッカケが「エッセイの公募で賞を取ったこと」でした。
エッセイの公募に挑戦した
今、小説家として活躍している人も…
「小説家になりたい!」と思っていた無名の時代があったわけです。
その方たちはどうやって作家になっていったのか。
芥川賞や直木賞の受賞を目指して、コツコツと作品を作っていた時期があったわけですね。
公募で賞を取ることは書き手として実力の証明になります。客観的な評価が信用につながります。
ぼくは「介護」をテーマにしたエッセイコンテストで賞を受賞しました。
また、介護のキャッチコピー公募で賞をもらいました。
賞を獲ったことをnoteの記事にして、結果的にエッセイが売れるようになりました。
公募に挑戦するとエッセイを書く力が身に付く
公募に挑戦するとですね…
文章力が飛躍的に向上します。
自分の書いたエッセイ。
審査員に選ばれることを意識して書くとなると、何度も内容を見直したり構成を考えたりするわけです。
要するに…推敲によってどんどん文章力が磨かれていくんですね。
だからマジで….公募に挑戦しましょう!
公募は実績だけでなく、賞金もゲットできます!
たとえ賞がもらえなかったエッセイだとしても…
作品がボツになってしまったとしても、
「これはいい作品だから大切にしたい!」
noteでエッセイを発表してしまえばいい
そう思えばnoteで有料記事として販売すればいいのです。
エッセイストになるために、公募は一石二鳥なのです。
こちらの記事で公募の探し方について解説していますので、参考にしてみてくださいね。
エッセイストになるために文章力を磨こう
面白いエッセイってどんなの?
あなたの中に「面白いエッセイ」の定義ってありますか?
ぼくの定義は…
- 人の感情を動かす文章
- 最後まで読まれる文章
ぼくはこのふたつを「面白いエッセイ」の定義としています。
文章表現や文体・構成はあくまでアクセントです。大事なのは最後まで読ませる文章力だと思います。
では文章力とはなんなのか。
どうしたら文章力は上がるのか。
ぼくなりの考えと実践になりますが、参考にしていただけると幸いです。
エッセイは感情表現するためにある文章
そもそも、エッセイとは何かっていうと、
自分の身の回りで起こった出来事から、自分の感情・思考を綴っていくこと
- 事象
- 心象
要するに、事象(出来事)と心象(自分の心の描写)が、読者に伝わることがエッセイストに必要な文章力だとぼくは考えています。
つまりエッセイは、感情表現なんですね。
エッセイは事象と心象のサンドイッチ
ぼくはエッセイをサンドイッチのイメージ書いています。
まず事象を描く
まず、目の前に起きている事象を的確に描写できる文章力が必要だと考えました。
たとえば、
テーブルの上に「りんご」があるとして、
赤い丸いりんごが木製のテーブルの上に乗っている。窓のから差し込む光を受けて影は少し伸びていた。
まず、読者に映像を伝えます。
そして心象を描く
そして心象を語っていきます。
ぼくはその赤いリンゴを見ただけで、口の中がほんのり甘く潤っていくのを感じた。
エッセイはこの事象と心象の繰り返し、つまりサンドイッチだと思っています。
そしてストーリーに乗せて構成することが文章力だと思っています。
エッセイが下手な人の特徴とは
エッセイを書き慣れていない人は、心象ばかりを語ってしまいます。
事象を伝えずに主観ばかりを語ってしまうと、読者は頭の中で映像が浮かばないんですね。
そうすると読者は置いてけぼりになって感情移入できません。しらけてしまうんですね。途中で読むことをやめてしまいます。
書き手は丁寧に「何対して」「どういう人が」「どんな状況で」「誰に対して」「どう思ったか」を書く必要があります。
まずは事象を正確に描写することを意識しています。
エッセイは、自分の書きたいことを書けばいいと思うのですが、読み手がいる以上、伝わるような書き方をしなくてはいけません。
そのために事象と心象の関係性を理解しておく必要があると思います。
田中さんの本はどれも面白い!さすがコピーライター。
情報やノウハウはエッセイにはならないんですね。
そこには感情が描かれていないからです。
細かい文章力のテクニックに惑わされないこと
やはり、エッセイの公募に挑戦することで実力は磨かれます。
また先ほどと同じことを言ってしまうかもしれませんが…
自分の好きなようにエッセイを書いていると、いつまで経っても実力は磨かれません。
文章力というと「文章の型」だとか「文末表現に気をつけよう」とか「てにをは」「比喩表現」などの細かなテクニックを追ってしまいますが、
それは後からついてきますし、すぐに身に付くものではありません。
公募の文字数制限で磨かれるエッセイストとしての文章力
公募には応募規定があります。これが文章力を磨いてくれるんです。
公募にチャレンジすると磨かれる技術について触れていきますね。
- 「実体験に基づいた内容に限ります」
- 「未発表の作品に限ります」
- 「Word縦書きでご応募ください」
- 「1,200文字以内で作品を仕上げてください」
このような応募規定があります。
中でも、文字数制限のある中で作品を仕上げることは、文章力を大きく向上させてくれました。
文字数制限があると「無駄な文章を削らなくてはいけなくなる」からです。
文章力のない人は書きすぎてしまう
エッセイを書き慣れていない人は、だいたい余計なことを書きすぎてしまいます。
余計な情景描写だったり余計な登場人物だったり…
文字数に収まらないどころかテーマもブレてきますし伝えたいこともどんどんボヤけてしまうんですね。
それは普段、自由なルールにもとにエッセイを書いてしまっているからです。
しかし公募で賞を狙うとなると、その余分な文章が命取りになります。
「一文一義」って聞いたことないですか?ひとつの文章にはひとつの情報だけを書きましょうって意味ですが。
エッセイも同じです。伝えたいことを簡潔に伝えている文章のほうが読みやすいんです。
こちらの記事でエッセイの推敲に関して、実際に賞を受賞したエッセイをもとに解説しています。
また、読者の感情を動かす文章構成についてもまとめています。
ぼくは推敲を何度も重ねて文章力が飛躍的に向上しました。自分で実感するくらいです。
とかく、書きすぎてしまいます。
この本は「いかに書かないことを意識するか」という視点で文章力が解説されています。
ライター出身の古賀さんだからこその視点でとても勉強になります。
まさに「文章を書く人のための教科書」です。
さらにエッセイを面白いエッセイに仕上げるために
やはり大事なのは、読者に最後まで読んでもらうこと。
読んでもらいやすい構成になっていること。先が気になる書き出しになっていることが大事です。
ぼくは映画の構成を参考にしています。
クライマックから始まる映画ってありますよね。
ラストシーンを最初に見せて「え?どうしてそうなったの?」みたいな映画です。アニメでもよくあります。
冒頭で主人公が不幸のどん底間まで落ちていったりして…感情の起伏をストーリーの中に組み込んでいくんです。
エッセイも同じで、読者の感情を動かすようにして構成されていたほうがいいと思っています。
ハリウッド映画の脚本の構成について解説されている本です。
コンセプトの作り方から主人公の設定まで、映画の制作の裏側を解説しています。
エッセイの参考になります。
エッセイは自分の体験談を語るものです。
小説は架空の主人公を設定してストーリーを展開していきます。
違うものですが、ストーリーの構成は小説を参考にするのはいいアイデアです。
読者が感情移入する構成の仕方を詳しく解説しています。
本を読んで文章力を磨く
書くこともだいじですが、おなじくらい読むことも大事です。
忙しくて本を読む時間がない。
そういう方は、音声で読書するのもいいですよ。
活字じゃなくていいの?って思うかもしれないですが、
エッセイで大事なことは、自分の意見や感情を育てることです。
本を聞いて知識を深め・思考を深めることは文章力の向上に繋がります。
聞く読書「オーディオブック配信サービス【audiobook.jp(オーディオブックジェイピー)】」を散歩しながら聞くのもおすすめです!
エッセイのネタをストックしておこう
ネタはエッセイの生命線です!
ぼくはとにかく、自分の感情が動いた瞬間に目を向けて・心を意識して生活を送っています。
日常生活でネタになるようなことはそんなに起こらない
ぼくは芸人をしていた時にネタを作っていました。
ネタ作りには相当苦労していました。
というのは、ただ普通に生活しているだけではネタになるような出来事はそんなに起こらないからです。
「すべらない話」のような、面白いオチになるような出来事は、そうそうありません。
かといって、
面白いアイデアが思いつくかっていわれると、それも思うように閃きません。
感情が動いた瞬間にメモを取る
ですが日常生活で感情が動く瞬間っていうのはたくさんあります。
たとえば「熱いなぁ〜」っていうのは感情の動きです。
「お腹すいたなぁ」「面白かったなぁ」「腹立つなぁ!」も感情の動きです。
なので、感情が動いた瞬間をメモする癖をつけています。
- 何に対して(事象)
- どう思ったか(心象)
を語ることがエッセイでした。
この感情の動きこそが、エッセイのネタになっていきます。
ぼくは日記を書くようにしています。日記に思考や感情・アイデアのメモを書き込んでエッセイのネタにしています。
何気ない日常がエッセイによってどんどん面白くなっていきます。
ふっと浮かんだエッセイのアイデアは、ものの数十秒で頭の中から消えてしまいます。
だからメモって重要なんです。一瞬のひらめきを失っただけで、もしかしたらベストセラーを逃しているかもしれません。
メモはエッセイだけでなく、仕事の場面においても重要です。
メモの重要性について理解が深まりますよ。
いつもとは違う体験をして自分の新しい感情を探す
行ったことのない場所へ行く。
出会ったことのない人に会いに行く。
体験したことのない経験をしにいく。
新しい仕事にチャレンジする。
どれもエッセイのネタになりそうですよね。
いつもと違うことをやれば発見や気づきがあり、新しい感情に出会う確率が高くなります。
たとえ物事が上手くいかなかったとしても失敗したとしても、エッセイのネタになると思ったら楽しめます。
そうして新しい感情をみつけ感情の幅を広げ・感情の高さや深さを追求していくことが、面白いエッセイ書くために必要です。
新しい自分に出会うことも、エッセイを書く醍醐味だとぼくは思っています。
介護の体験をエッセイにしています
ぼくはというと、介護をテーマにしたエッセイを書いています。
介護施設・デイサービスで働く介護職員です。
介護現場では、認知症の方や身体疾患により介護が必要な方しかいないので、ほんとうにいろんな出来事が起こります。
命を扱う現場なので、これでもかっていうくらい感情が揺さぶられます。
ぼくはこの介護施設での体験がエッセイストとしの生命線になっています。
「あ、あれなんていうんだっけ…」
「たとえばあれは…」
みたいな…エッセイには、分かりにくいこと・伝わりにくいことを、相手に伝わるように表現することが求められます。
言語化できるスキルを身につけておくと、エッセイに独自性が生まれてくると思います。
あなたしか書けないエッセイを目指しましょう。
ぼくもぼくにしか書けないエッセイを目指しています。
書き手として執筆範囲を広げよう
エッセイだけにこだわらずに、いろんな文章に挑戦してみましょう!
世の中に、書く仕事を沢山あります。
ぼくはエッセイを書きながら、Webライターの仕事をしていますし、キャッチコピーを書いたりもします。
ぼくが経験したことある書く仕事をいくつかご紹介しますね。
企業で広報・PR記事を書く
企業の中に広報・PRの部署があるなら、社内で書く仕事をするという選択肢もあります。
ぼくは前職の会社でキャッチコピーを書きました。
「企業メッセージ」や「ブランドコンセプト」といったコピーライティングも、エッセイを通じている部分があります。
- 何を
- どう伝えるか
エッセイであろうが企画書であろうが提案書であろうが、文章の本質は変わりません。
ぼくはコピーライター養成講座でそのことを学びました。
中小企業で社内にコピーライターがいる企業はほとんどありません。
だからこそ、文章を書ける人材は価値が高いのではないでしょうか。
SNSやホームページを使った情報発信ができる人は、より重要なポジションを任されると思います。
エッセイにとどまらず、広報・PRなどの文章にも挑戦してみましょう。
クラウドソーシングで書く仕事を探す
クラウドソーシング(クラウドワークス)で書く仕事を検索すると、書く仕事はたくさん見つかります。
- YouTubeの動画シナリオ作成
- SNSの投稿代行
- 企画書の作成
- 音声メモの書き起こし
ぼくは介護系Webライターとして記事の執筆をしています。
書く仕事を副業にしてみたい方は、まずクラウドワークスに登録しておきましょう。
個人ブログで文章を書く
このブログは、広告の掲載をしています。いわゆるアフィリエイトです。
ブログを書くことも、文章で収入を得るという仕事と言えます。
ブログを書くにしても文章力が必要になってくるので、エッセイと並行して個人ブログを開設して記事を書いてもいいですし、単なる趣味で書くのもいいと思います。
個人ブログを開設するのはものすごく簡単です。
ドメインを取得しサーバーを契約すれば、ブログは1日で開設できます。
明日からブログを書けますよ!
Webライターに挑戦したい人。
ブログに挑戦したい人は、Webライティングを身につけておくといいですよ。
Googleの検索エンジンに評価される文章の書き方には、SEOという特別なルールがあります。
この本はWebライティングのノウハウがかなり細かく解説されています。
インターネットで文章を書く方におすすめの一冊です。
Kindle(キンドル)でエッセイを出版する
noteで書き溜めてきたエッセイ。
ぼくはいずれ、AmazonのKindleで、本を出版したいと考えています。
そうした目標を立てながら、毎日noteでエッセイを書いています。
あなたたも、一緒にnoteで創作してみませんか?
noteのメンバーシップでは、創作のアイデアや大喜利コンテンツを発信しています。
よかったら、ぼくのnoteに遊びにきてくださいね!
エッセイストになるにはエッセイストを名乗る
エッセイストにならなくても、書くことにはものすごく大きなメリットがあります。
思考を頭の中から取り出して文字にするという行為は、物事を主観から切り離して客観視するということです。
「しゃべったらスッキリした!」っていうじゃないですか。
これだけで悩みや不安が軽くなりますし、解決方法が見つかったりします。
あれって主観の思考を吐き出している行為だと思うんですよね。
人に話すことで共感を得られますし、誰かと一緒に解決法を探すきっかけになります。
エッセイて、人生を豊かにしてくれるんです。
話すことが苦手な人は、書くことでストレスを発散しましょう。
そして「わたしはエッセストになりたい!」そう思うのであれば、
エッセイストを名乗って、エッセイを発信し続けましょう。
あなたの書いたエッセイが人の心を動かすものならば、きっと誰かが見つけてくれるはずです。
ひとりで挑戦するのは心細いですよね。
一緒にがんばりましょう!
ぼくもエッセイストを名乗ってエッセイを書き続けます!
最後まで読んで頂いて、ありがとうございました。