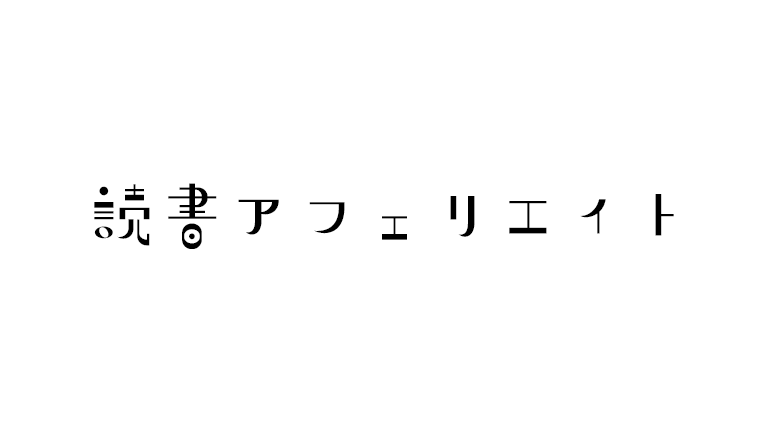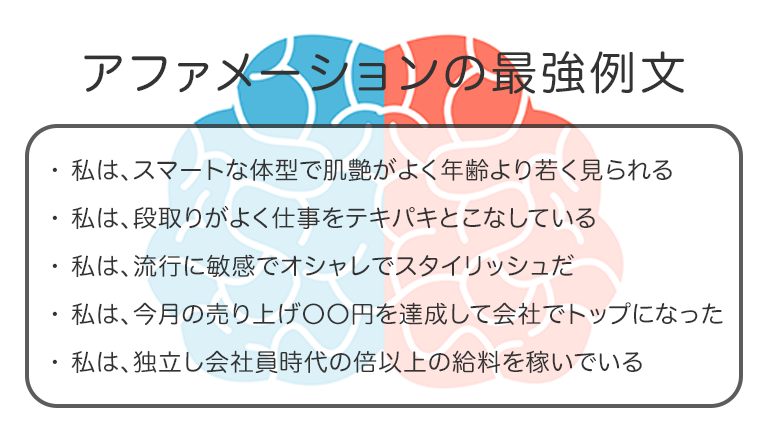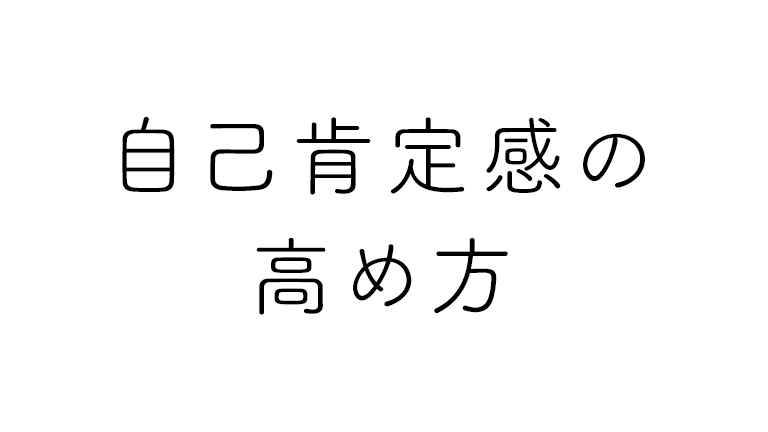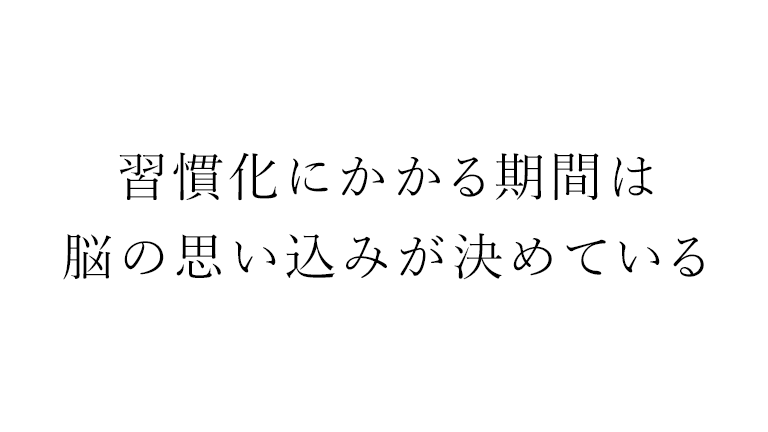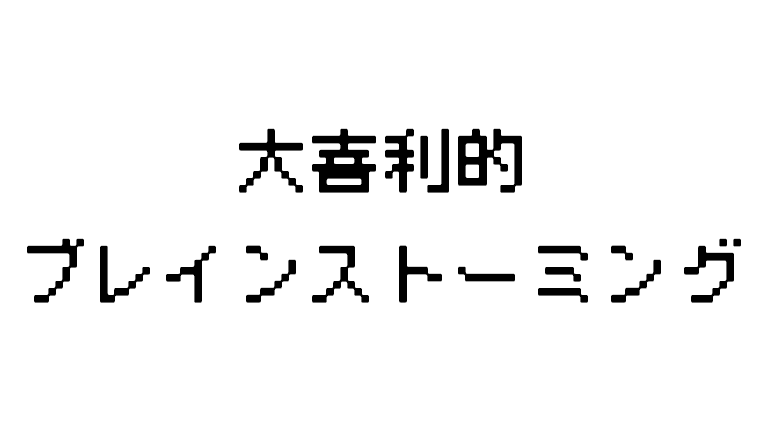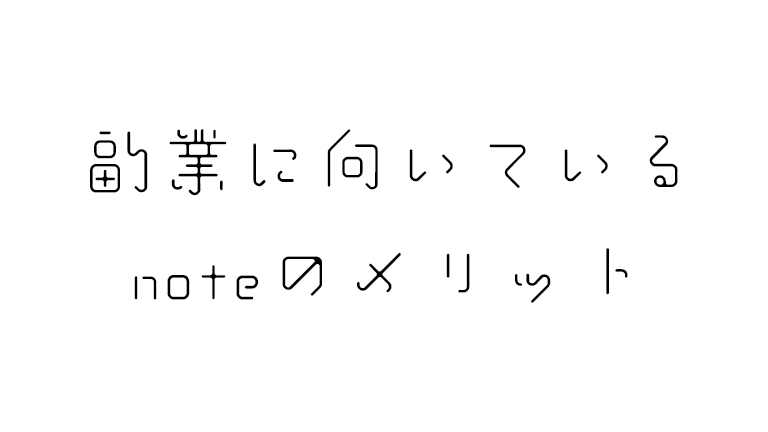強いチームをつくるチームビルディングの方法
働きやすい職場にするために意識することはなんでしょう。
チームが成果や結果を出すために必要なことはなんでしょう。
ぼくは人間関係だと思っています。一緒に働く仲間の存在が、仕事の内容よりも大切です。
今、あなたが働いている職場の仲間・人間関係はどうですか?
会社やグループ・家族や友人との集まり。強いチーム・成果の上がるチームには、個々の能力を最大限に引きだす仕組みがあります。
そんなチームになるための方法が、チームビルディングです。

こんにちは、のざき寿(ひさし)といいます。元芸人です。
ぼくがチームビルディングと出会ったのは、ホームページ制作会社に在籍しているときでした。
ホームページ制作の仕事は、営業・ディレクター・デザイナー・エンジニアなど工程ごとに分業されています。
個人のスキルが重視されるので、協力体制が築きにくい側面があるんですね。自分の仕事さえこなしていれば問題ないという仕事のスタイルです。
しかし品質や納期など他社を上回る成果を出さなければ、他社に遅れをとってしまいます。そこで成果を出す強い組織を作るために、会社としてチームビルディングを学ぶことになりました。
チームビルディングで重要なことは、一緒に働く仲間の能力や価値観を知ることです。そして良好な人間関係を築くことです。
あなたは、一緒に働く仲間のことをどれだけ知っていますか?
仲の悪いメンバーが集まると、足の引っ張り合いが始まります。
仲の良いメンバーが集まると、協力し助け合います。
チームビルディングにおけるチームとグループの違い
さて、チームビルディングを語るまえに、チームとは何かについて語る必要があります。
チームと同じような言葉に、グループがあります。
チームとグループの違いはなんでしょう。
- グループ:ただの人の集まり
- チーム:同じ目的・目標を持った人の集まり
つまりチームには目的・目標が必要ということです。
会社は売上目標や社会貢献などの目的・目標があるのでチームです。家族なども子育てという目的があるのでチームといえますね。
一方、大学のサークル活動はグループです。コミュニティや情報交換のための集まりもグループですね。
プロ野球はチームです。
草野球はグループです。
仲良しクラブではないということです。
どうですかね?伝わりましたでしょうか。
チームビルディング必要な目標設定とは?
チームに必要な目標についても理解しておきましょう。
チームビルディングにおいての目標とは目指すべきゴールのことです。
プロ野球のチームでいうならリーグ優勝や日本一をめざすこと。サッカーならワールドカプ制覇になるでしょう。チームは目標があると結束し、成果というゴールに向かって動き出します。
あなたの所属しているチームは、目標設定がしっかりできていますか?
意義目標とは?
意義目標は、抽象度の高い目標のことです。特徴としては以下の通りです。
- 抽象度が高い
- 指標や行動を自分たちで考える必要がある
- 成果目標や行動目標を通じて達成したい事の先にある目標
企業でいえば、存在意義(ブランドパーパス)やビジョン・ミッションに相当します。
ひとつ具体例を挙げてみます。
水と生きる
サントリーホールディングス株式会社
意義目標は抽象的な目標や概念を表現するものです。抽象的で幅広い解釈ができるので、自由な発想がしやすく、新しいアイデアが生まれます。
しかし意義目標は抽象度が高すぎる目標のため、具体的な行動に結びつきづらいことが欠点です。
成果目標とは?
成果目標は、目標達成の具体的な数値や期限などのことです。
- 数字などの指標が定められている
- 目標の達成条件が設定されている
日常的に目にする目標は、成果目標であることがほとんどです。
- 売上を前月比120%達成する
- 納品までのリードタイムを5%短縮する
- 生産効率を〇〇%向上させる
意義目標と次に紹介する行動目標の中間的なところに位置しています。
行動目標とは?
行動目標は、業務に直結した内容で日々の行動や具体的な作業のことです。
- 具体的な作業・行動を決める
- 意義目標や成果目標を達成するための目標
- 個人個人の行動を明文化したもの
具体的な例としては、以下のようなことです。
- 企業の事業のサポートをするためにWeb制作をする
- 会社を知ってもらうためにブログを書く
行動目標は、行動が具体的なため判断に迷う事がありません。しかし行動が限定されているため、画期的なアイデアは生まれにくいデメリットがあります。
チームビルディングは意義目標がもっとも重要
各目標の中でも特に重要なのが意義目標です。
抽象的な目標から具体的な目標や課題を見つけ出すことが大切だからです。
目標の設定は、チームビルディングにおいて出発点になります。
あなたのチームの目標はどうでしょうか。意義目標・成果目標・行動目標の視点から、目標を見直してみましょう。

チームビルディングは、人・関係性・仕組みで支えられている
ここからチームビルディングの本質について語っていきます。
チームビルディングは、三つの構成要素で支えられています。
- 人:人材
- 関係性:人間関係
- 仕組み:評価制度
それぞれ、詳しくみていきましょう。
人とは、人材のこと
チームを構成するのは人です。チームビルディングは、自身を含めたメンバー・仲間の強みや長所を知ることからはじまります。
- 仲間の強みと長所
- 仲間の得意なこと・苦手なこと
- 仲間の考え方・価値観
では、どのようにして仲間のことを知っていばいいか、具体的な自己診断の方法やツールを紹介していきます。
あなたが感じる主観的な解釈は置いて、客観的に判断することがポイントです。
人の思考特性を知る、ハーマンモデル(利き脳診断)
ハーマンモデルは、人の「利き脳」を知るための診断です。
ノーベル賞科学者ロジャー・スペリーなど、大脳生理学の研究成果をもとに、ネッド・ハーマンにより開発されました。
このハーマンモデル診断は、IBM・マイクロソフト・資生堂などの企業研修で採用され、世界各国で200万人以上の利用実績がある信頼性のおける診断です。
人には利き腕や利き目・利き耳があるように、思考にも利き脳があります。利き脳がその人の思考特性を決めているといわれています。
人の思考特性は、論理的思考の左脳、抽象的イメージの右脳に分かれ、さらにコミュニケーションや意思決定・問題解決・マネジメントスタイルなど、4つの部位から構成されます。
- 大脳新皮質側の左脳
- 辺縁系側の左脳
- 辺縁系側の右脳
- 大脳新皮質側の右脳
人は、自分の利き脳にあった活動であれば苦痛を感じることなく作業に集中でき、高いモチベーションの高いまま仕事や勉強をすることができます。
一方、自分の利き脳に合わない行動は苦手意識を感じ、やる気も起きにくい状態にしてしまうのです。
人の得意分野を知る、ストレングス・ファインダー
ストレングス・ファインダーは、自分の強み(ストレングスポイント)を知るためのツールです。
人は長所を伸ばすよりも、欠点を克服するための努力に多くの時間を割いています。
ストレングスファインダーは、自己診断のために180問の質問が用意されています。診断の結果を34の長所となる資質に当てはめ、あなたの得意分野を科学的な視点で導いてくれます。
チームビルディングでは、各メンバーが長所を最大限に活かすことが重要です。まずはメンバーの長所を把握し共有しましょう。
人の性格を知る、エニアグラム診断
エニアグラム診断は、人間の性格を9つのタイプに分類する診断です。
9つのタイプに分かれた20の質問、合計180の質問に答えることで性格を診断します。
ものごとへの感じ方や感情・感性を知るために有効な診断です。
- 完全でありたい人
- 人の助けになりたい人
- 成功を追い求める人
- 特別な存在であろうとする人
- 知識を得て観察する人
- 安全を求め慎重に行動する人
- 楽しさを求め計画する人
- 強さを求め自己を主張する人
- 調和と平和を願う人
チームビルディングにおいて、相手がどんな価値観を持ちどう感じているかを考えることはとても重要です。
エニアグラム診断は、発言や行動の裏にどのような心理が働いているか、知る手がかりになります。

コーチングで仲間のタイプを知る
コーチングは、人を4つのタイプに分類します。タイプによって掛ける言葉や行動に気を配ることがチームの人間関係を良くします。
- 実行力でチームをリードするコントローラー
- 夢を語って盛り上がるプロモーター
- 合意と協調を重んじるサポーター
- 冷静沈着に現状を分析するアナライザー
メンバーでコーチングのタイプを共有し、互いの価値観を尊重したコミュニケーションを大切にしてください。
紹介した診断をすべて実践する必要はありません。組み合わせて診断することで客観的な視点を持って、人間関係を見つめ直すことができます。
会社では会議やレクリエーションの一環として、気軽にやってみることをお勧めします。

関係性とは、人間関係のこと
つぎに人間関係について掘り下げて考えてみましょう。
職場の良好な人間関係とは、仲間とのコミュニケーションでストレスを生まない環境だと思っています。
そのために大切なことは、チーム内の心理的安全性を保つことです。発言や意見を言いやすい環境、つまり居心地のいい環境を作ることが重要になってきます。
チームの心理的安全を保つ
心理的安全性は、組織行動学を研究するエドモンドソン氏が1999年に提唱した心理学用語です。チーム内で他のメンバーが自分の発言を拒絶したり罰したりしないと確信できる状態と定義されています。
有名な事例に2012年、Googleの心理的安全を重視した組織運営が挙げられます。
Googleの調査・検証が世界に広がったことで、心理的安全性は組織経営において重要視されるようになりました。
Googleのように精鋭を集めたチームでも、心理的安全性が低い職場では生産性が上がらないと結論づけられたのです。
心理的安全に奪う原因は主に4つあります。
- 無知だと思われる不安
- 無能だと思われる不安
- 邪魔だと思われる不安
- 批判的だと思われる不安
これらの不安を取り除くことが心理的安全性を保つ上で重要になります。
心理的安全性の効果としては、パフォーマンスが向上・活発な情報交換・新たなイノベーションの創出などがあります。
あなたが所属するチームの心理的安全性はどうでしょうか?
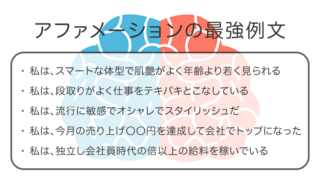
仕組みとは、システムのこと
チームには、ルールや規則・秩序が必要です。自分勝手な行動をしたときには、注意をうながしたり、客観的に評価したりする基準や指標・仕組みが必要です。
ここでは、チームの仕組みづくりにおけるチェック項目を挙げていきます。5w1hを使って考えていくと整理しやすいでしょう。
- What:何をルール化するのか
- Who:誰が決めるのか
- Where:どこまで責任を負うのか
- When:どのくらい確認するか
- How:何を評価するのか
What:何をルール化するのか
- 人の全ての行動を監視するか?
- やらない事、禁止事項は?
Who:誰が決めるのか
- リーダーが決めるのか
- 多数決で決めるのか
- 個人個人に任せるのか
Where:どこまで責任を負うのか
- チーム全体の責任なのか
- 個人の責任なのか
When:どのくらい確認するか
- 月一で見直すのか
- 年単位で見直すのか
How:何を評価するのか
- プロセスを重視するのか
- 成果を重視するのか
チームにおいて禁止されること・推奨されることを考えていきましょう。
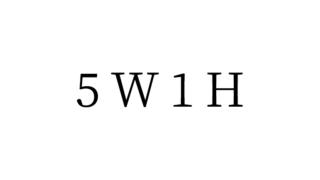
チームビルディングここまでのまとめ
ぼくが会社でチームビルディングを行なったときは、半年間をかけてじっくり取り組みました。
- 自己診断ツールを使って自分を知る
- メンバー同士で強み・価値観を共有する
- 心理的安全性を作るために交流会などを行う
- チームとしての決め事をルール化して言語化していく
このようなプロセスでチームビルディングを行いました。
その会社はちょうど事業拡大の転換期でした。経営指針やビジョン、行動指針を刷新するためのプロジェクトの一環でチームビルディングに取り組んだのです。
チームビルディングは、会社のインナーブランディングにも役に立つと思います。

チームビルディングが長期間にわたる理由とは?
チームビルディングは長期に渡るプロジェクトになります。
最低でも半年から1年くらいの期間をかけて取り組むべきでしょう。
なぜそれだけの期間がチームビルディングに必要かというと、人やチームには成長する過程がり、短期間で意識を変えることは難しいからです。
チームが今、どの成長過程にあるかを把握するために、タックマンモデルとホメオスタシスについて知っておくといいでしょう。
チーム変革までの道のり
成果を上げるチームになるまでには、次のような段階があります。
- 個人の気づき・意識変化
- 個人の行動・習慣が変わる
- チーム全体が変わる
いちばん最初の変化は個人の変化です。個人が変化しないかぎりチームの変化はありません。では個人はどのように変化していくのでしょうか。
個人のパフォーマンスが発揮されるまで
人は意識が変わればすぐに成果がでる訳ではなく、物事が身につくまでに数々の段階があります。「知らない」から「理解している」「できている」になるまでには、多くのステップがあります。
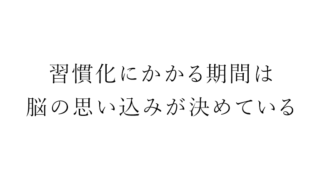
人間にはホメオスタシスという一定の状態を維持しようとする働きがあります。人の行動は無意識に定着してからやっと表に現れてくるのです。
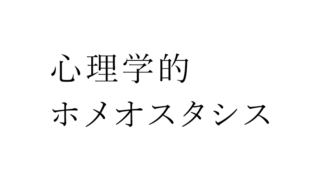
タックマンモデルでチームの状態を把握する
個人が変化した後は、チーム全体が変わる必要があります。
タックマンモデルとは、チームが成熟するまの5段階のステージを表現したものです。1965年に心理学者のタックマンによって提唱されました。
- STEP1 形成期
- STEP2 混乱期
- STEP3 統一期
- STEP4 機能期
- STEP5 散会期
タックマンモデルを理解することで、チームの状態が不安定になっても冷静に対処出来るようになります。
STEP1 形成期
チームが立ち上がったばかりのタイミング。メンバーのコミュニケーションやチームとしての目標を探っている時期。
STEP2 混乱期
チームの目標や各自の役割・責任について混乱や意見の対立が起こるタイミング。メンバー同士本音で語り合う期間ともいえます。
STEP3 統一期
目標や役割などの共通認識がとれメンバー同士の相互理解や尊重が生まれる期間。
STEP4 機能期
チームが成熟してリーダーの指示がなくともメンバーが各々の役割を果たし、自律して行動できる期間。
STEP5 散会期
目的を達成し時間的な制約・期限を受けてチームが解散してしまう期間。
この5つのステップを知りメンバー内で共有できると、客観的な視点で冷静な判断が下せるようになるでしょう。

働き方が多様になった今、チームビルディングが必要です
2020年以降、働き方が大きく変化しました。
在宅勤務が広がり、オンラインで対面せずに仕事を進めていくことが多くなってきています。
自宅にこもってひとりで仕事をしていると、他人との繋がりを感じにくく組織やチームで働く意味が感じられなくなってきます。
また個人事業主やフリーランス・副業するひとも増えてきました。
しかし人が集まればチームなのです。今後はより一層チームビルディングの重要性が高まっていくでしょう。
成果の出るチームを作るために、チームで必要とされる人材になる為に、チームとは何かを学んでおくとこはとでも大事なことです。
そして良好な人間関係を築き、人間関係のストレスが少ない時間をすごしましょう。
あなたも今すぐチームビルディングに取り組んでみてください。あなたが変わればチームも変わっていきます。