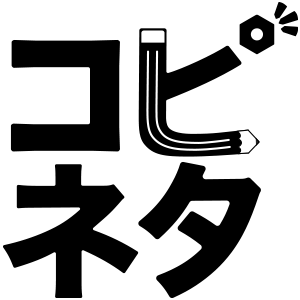習慣化までの期間を短くする方法・成し遂げた自分を想像して楽しい人生にしよう
習慣化の期間を短くするために行ったことは、
自分の思い込みを変えることでした。
習慣化できている自分を想像できるようになると、行動も一緒についてくるようになりました。
思い込みの強さというか脳内のイメージが書き換われば、それに応じて習慣化の期間は短くなるということを実感しました。
お酒・喫煙をやめて、運動習慣・読書週間・エッセイの執筆やギターなど、さまざまな習慣を身につけてきました。
お酒は、毎日のように飲んでいました。
健康のことを考えて、ずぅーっとやめたいなぁと思っていたのですが、なかなかやめられませんでした。
1週間がまんしてみるものの、ちょっと気を抜いた瞬間とか仕事で疲れた週末なんかに、やっぱり飲みたくなるわけです。
「1日くらい飲んでもいいかなぁ」
と、飲んでしまったが最後。それからまたやめられない日々が続いていきました。そんなことを数年繰り返し、結局やめられないままずっと過ごしていました。
でもやっぱりお酒やめたいなぁと思い。
習慣化についての本だとか動画だとかを見まくった結果、あることに気づきます。それは、
「我慢しているといつまで経ってもやめられない」ということ。つまり習慣化できないということです。
自分の意識を変えない限り、習慣化できないことを理解しました。
それから、思い込みを変えることを意識して毎日を過ごした結果。数年がかりでやめられなかったお酒を一ヶ月以内でほぼやめることに成功しました。お酒をやめたことで体重も減りダイエットにも成功しました。
習慣化での最大のメリットってなんだと思いますか?
習慣の積み重ねが人生をつくっています。習慣が変われば人生が変わるということです。
単純な話、いい習慣を身につければいい人生になるということ。
この記事では、習慣化の方法と習慣化にかかる期間を短くする考え方やコツを紹介していきます。
そもそも習慣化とは?どのくらいの期間が必要?
意識しなくても無意識で行動のことを習慣・習慣化といいます。
無意識とは、意識しないで行なっている行動のことです。
日常の具体的な行動としては、風呂や歯磨き・着替えなどで「どうやって着替えたらいいんだっけ」って考えることってないですよね。
逆に「まず、野菜を水洗いして、薄くスライスして千切りにする」みたな、頭の中で工程を意識するようなことは、顕在意識と言います。
習慣化には3つの種類がある
習慣化は次の3つの特性に分かれます。
ロンドン大学のフィリッパ・ラリー博士「人間の習慣化」によって提唱されました。
- 行動習慣
- 身体習慣
- 思考習慣
大まかに運動習慣と思考習慣に分かれていて、
運動習慣はランニングとか筋トレとかでしょうか。思考習慣はプラス思考とかマイナス思考とかそういったことを指しています。
また、習慣化させるためのアプローチがそれぞれ変わってくると言われています。
習慣化にかかる期間は平均66日
研究結果によると、いずれの習慣化も平均してふた月ほどの期間がかかると言われています。
行動習慣を習慣化するまでの期間
学習や読書などの習慣です。1ヶ月程度の期間を要するといわれています。
身体習慣の習慣化するまでの期間
運動や早起きなど、人間の生理現象や体調に関わるような習慣です。3ヶ月程度の期間を要するといわれています。
思考習慣の習慣化するまでの期間
思い込みや意識などの習慣です。6ヶ月程度の期間を要するといわれています。
なぜ習慣化に失敗してしまうのか
意識の変化がないまま、我慢して習慣化しようとするとだいたい失敗に終わります。
結局、無理をするとストレスが溜まって爆発するということですね。
たえるなら、風船を膨らまし続けるとそのうち爆発しますよね。我慢をして習慣化している状態っていうのはそういうことです。
「毎日の積み重ねで習慣化できます」なんてよく目にしますが、あれは嘘です。
「お酒飲みたいけど、今日は我慢しよう」と、毎日努力していても、いずれ精神の限界を迎えてしまうということです。
そうではなく、風船自体をなくしてしまうことを考えなくてはいけません。
「お酒?なにそれ?」
これはちょっと言い過ぎかもしれませんが、ぼくはそのような感覚でお酒をやめました。
要するに意識を180度変えることに焦点を当てて習慣化をしていくことが重要なんです。意識を変化させないで行動だけ積み重ねる習慣化はうまくいきません。
ぼくはそれでずっと習慣化に失敗してきました。
では、ぼくが考える習慣化のコツについて解説していきますね。
習慣化までの期間を短くするために潜在意識を活用しよう
ぼくは「どのようにしてお酒をやめたのか」について解説していこうと思います。
お酒をやめることだけでなく、喫煙やダイエットにも有効な考え方だと思うので、置き換えて読んでみてくださいね。
アルコール・お酒は体によくないってことを思い込む
これが結論と言っても過言ではないのですが、
「お酒は体に良くない」ってことを思い込みました。これは「お酒を我慢する」とは、根本的に考え方が違います。
「お酒は飲みたいけれど健康のために我慢をしよう」そういう考え方ではなく、お酒自体を良くないものとして認識し、意識自体を変えていくことを実践しました。
つまり禁酒ではなく、お酒自体のイメージを書き換えて、お酒をやめるということです。
良くない根拠を集める
とはいえ、そう簡単に意識を変えることは難しいので、まずはお酒に対する知識や情報を集めていきます。
- お酒を飲むと楽しくなる
- ビールは美味しい
- お酒のつよい男性はかっこいい
- ストレス発散になる
このイメージを、次のように書き換えていきます。
- お酒は栄養がない
- お酒を飲むと内臓にダメージが残る
- お酒の席では喧嘩が起こりやすい
- 二日酔いで余計にストレスになる
- 酔っ払うと何もしたくなくなる
こうしてお酒のデメリットとなる根拠を集めていき、イメージを少しずつ変えていきました。
すると次第に「お酒を飲むことにメリットはない」と認識するようになり、行動に変化が現れてきます。
意識に変化があると行動も変わってくる
コンビニでお酒をみるだけで「体に悪いよなぁ〜」と負の感情を抱くようになってきました。
「これを飲んだら次の日体が疲れるよなぁ」とか「アルコール飲み続けたら、絶対体悪くするよなぁ」とか、いままでお酒に感じていた感情とは違う感情になってきます。
「お酒を飲む」という習慣が「お酒を飲まない」という習慣にちょっとずつ変化していきました。
習慣化のカギとなる潜在意識とは
習慣化する方法は次のふたつのパターンしかありません。
- 行動から先に変えるか
- 思考から先に変えるか
ぼくは思考を先に変えることをお勧めします。
潜在意識が「お酒は体によくないし、いいことは何もない」と書き換われば、行動は自然についてくるというわけです。
潜在意識が書き換わっていくプロセス
潜在意識が書き変わっていくプロセスには次のような工程があります。
- 習慣化した自分をイメージできるようになる
- 今の自分と理想の自分と差を認識できるようになる
- 理想の自分を実現するために潜在意識が働く
こうした心理的な変化を経て潜在意識は書き換わっていきます。心理的なプラシーボ効果やホメオスタシスが働きます。
目的や思いの強さによって、習慣化までの期間は短くなっていきます。
習慣化の目的をしっかり持つ
なんのために習慣化したいのか
習慣化した先に自分はどうなりたいのか
このふたつを明確にしておくことが大事です。
ぼくがお酒をやめようと思った目的は、お酒を飲むことによって仕事のパフォーマンスが落ちることが嫌だったからです。
お酒を飲むと頭が働かなくなり、何も作業したくなくなります。二日酔いになると次の日の午前中は仕事が手につかず、多くの時間を無駄にしてしまいます。
お酒を飲むメリットもありますが、それを差し引いてもデメリットの方が大きいと思ったのでやめようと思いました。
そして目的を達成した時のイメージを頭の中で描きます。そうすると潜在意識は徐々に書き変わっていきました。
お酒をやめてどうなったか
いちばん大きな変化は、体重が落ちたことです。
3ヶ月で5キロのダイエットに成功しました。体は軽くなりましたし、内臓も疲れにくくなりましたし睡眠の質も上がりました。
そういえば出費も少なくなりましたね。飲みに行ったりすることがなくなって、ほとんどお金を使うことがなくなりました。
飲みに行っていた時間は、公募やキャッチコピー制作の時間に充てています。Webライティングの副業の時間できました。
習慣化の期間を短くするモチベーションの正体を知ろう
習慣化するためには、モチベーションを高く保つことが重要になってきます。
まずはモチベーションの正体を知ることからはじめましょう。
モチベーションとは何か
目的やゴールを達成するためのエネルギーのこと。
そのエネルギーの原動力には「報酬」と「身の危険」があります。
「報酬」が習慣化のモチベーションを高める
報酬とは、習慣化をすることで得られる成果・結果のことを意味します。
あなたはタダ働きをずっとできますか?
働いたなら働いた分だけの給料や見返りが欲しくなりますよね。何の成果や結果も得られないまま努力を継続することは不可能ですよね。
- 食事管理を習慣化すれば、スリムな体型が手に入る
- スキル学習を習慣化すれば、評価され給料が上がる
- 運動習慣を習慣化すれば、健康的になる
習慣化の先には必ず報酬が必要です。報酬があるからこそによって高いモチベーションが維持できるわけです。
また報酬を得るために集中力が高まっているとき、脳内では、やる気・幸福感を感じさせる物質であるドーパミンが放出されます。
たとえばスマホゲームのガチャシステムは、報酬と習慣化をうまく利用しています。
「危険」も習慣化のモチベーションを高める
逆に、危険もモチベーションを高める要因になります。つまり「変化しなければならない危機的状況」が習慣化を後押しするのです。
- 肥満による生活習慣病でダイエットが必要になった
- 健康のために、禁煙・禁酒を医師から忠告された
- 時代の変化に取り残されないように情報収集が必要だ
「〜しなければ危ない」と危険を回避するための欲求、要するにモチベーションが高まるわけです。
危険回避のときに放出される物質は「ノルアドレナリン」。ノルアドレナリンは交感神経の情報伝達物質で「闘争または逃走」の役割を担っています。血圧の上昇・心拍数の上昇が起こります。
モチベーション正体はホメオスタシス
道で転んで、足や腕に擦り傷をしたときを想像してみてください。
しばらくすると血は止まり、傷口は瘡蓋になって自然に治ります。これは人間に備わっている自然治癒力のおかげです。自然治癒力に「皮膚は傷のない状態が正常である」とプログラムされているから起きます。
この「人間が一定の状態を維持しようと変化を拒む働き」をホメオスタシス(生体恒常性)といいます。
実はこのホメオスタシス。習慣化と密接に関係しています。
なりたい自分の姿を、脳・潜在意識に思い込ませ記憶させます。するとホメオスタシスが発動し「理想の状態が正常である」と、現状の自分と理想の自分との差を埋めるように勝手に働いてくれるのです。
このホメオスタシスの機能を、人はモチベーションと呼んでいるのです。
習慣化までの期間を短くする具体的なコツ
では、ぼくが習慣化するときに意識している具体的なコツや行動について紹介していきたいと思います。
アファメーションする
アファメーションとは「理想の姿を手に入れるためのポジティブな宣言」をすることです。
習慣化できた自分をイメージする言葉・文章を考えて毎日言葉にしていると、次第に脳内で達成した姿を想像できるようになってきます。
つまり、潜在意識や思い込みを書き換えることにつながります。
脳が楽しいと感じることをしよう
そもそも、楽しいと感じること・やりがいを感じることでないと習慣化しても達成感がありません。
- スマホゲームにハマってしまう
- 漫画を徹夜して読んでしまう
これらは、脳が「楽しい」「ワクワクする」と感じるからついついやってしまう行動なのです。
たとえばダイエットするにしても、体重計に乗ったときに「おお!1キロ減っている」とか「体重を維持できている!」とか、楽しむことが大切なのです。
ぼくがお酒をやめたときも「やっぱり体が軽い!」って思うことが多くなって、楽しみながらやっていましたし、
それこそギターなど、物事を身につけていく趣味なんかは、上達していくことを楽しむことが習慣化のポイントになってきます。
悪い習慣は習慣化の邪魔をする
新しい習慣を取り入れることもそうですが、まず今までの習慣を捨ててスペースを空けておくことも大事です。
- 夜ふかしをやめる
- TVは時間を決めて観る
- 食べすぎ・飲みすぎをやめる
ぼくはこれらの習慣をやめました。
悪い習慣を捨てると時間と心に余裕が生まれます。まずは余白をつくりましょう。
小さな成功だけに目を向ける
「ジャージに着替えることはできた」とポジティブに考えるか。
「ジャージに着替えただけで終わってしまった」とネガティブに考えるか。
できなかったことよりも、できたことに意識を向けるようにします。
どれだけ些細な行動でも、習慣化できた事実には変わりません。
習慣化に失敗する人のほとんどが、初期衝動で大きくやりすぎてしまい短期間で燃え尽きてしまいます。
習慣化にチャレンジし始めたときはとくに、小さな成功だけに目を向けて一歩ずつ進んでいきます。
失敗しても何度でもチャレンジすればいいだけのこと。それが習慣化への近道です。
ゲーム感覚で習慣化の期間を短くする
中間目標を設けましょう。自分へのご褒美も必要です。
- 1週間継続で自分へご褒美
- 1ヶ月間継続で自分へご褒美
- 3ヶ月間継続で自分へご褒美
達成するごとに自分を褒めるようにしましょう。
心理的トリガーでモチベーションを上げる
- この曲を聴くとモチベーションが上がる
- この映画を観るとワクワクしてくる
- この食べ物を食べると元気になる
感情がポジティブになるきっかけのことを「心理的トリガー」といいます。
テンションが上がらない時は活用しましょう。
自分の外側に習慣化の理由をつくる
習慣化の理由を「自分の外側」につくることは効果的です。
他人に見られている・監視されている状況をつくると、手を抜くことが難しくなります。
強制的にやらざるを得ない状況を作るのです。他人の力を上手に利用するのです。
- 目標を他人と共有する
- SNSで報告するようにする
- 一緒に頑張る人を探す
外に向けた発信をすることで、やらざる終えない状況をつくっているのです。
習慣の積み重ねが人生そのもの
結局のところ、人生は習慣の積み重ねで成り立っていると思うのです。
いい習慣をひとつでも多く身につけよう。
悪い習慣はひとつでも多く手放そう。
いい言葉を使う人は、いい人格をしている。
悪い言葉を使う人は、人格に難がある。
もし、あなたの人生が思い通りの人生になっていないとしたら、習慣を見直すことで軌道修正できるかもしれません。
何かを成し遂げるには、習慣の積み重ねでしか到達できないことがほとんどだと感じています。
ぼくも毎日、習慣を積み重ねていきます。そしてあなたの成功を祈っています。