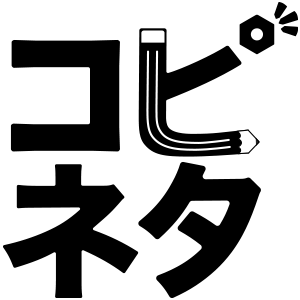宣伝会議賞2020・キャッチコピー公募に初挑戦したら三次審査まで通過した
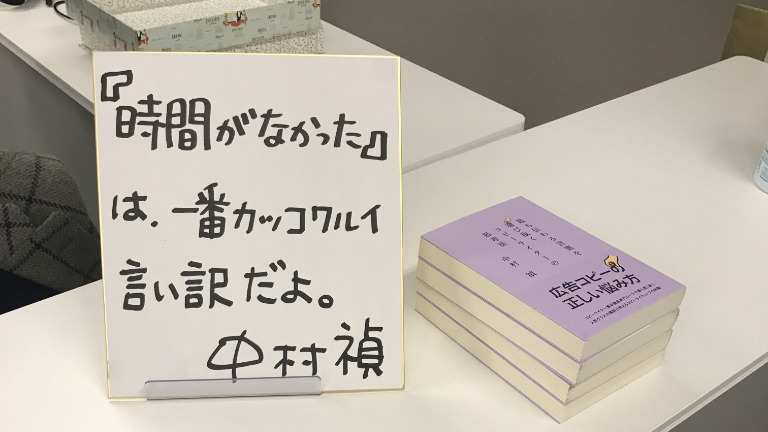
握手は綺麗な手で
課題:社会情報大学院大学
このキャッチコピーが、宣伝会議賞2020・三次審査まで通過しました。宣伝会議賞は初挑戦だったので、参加することに意味があると思って応募しました。
こんにちは、のざき寿(ひさし)といいます。元芸人です。
けれど三次審査通過を知ったとたん「あともう一歩でファイナリストの可能性もあったのかぁ」と欲がでてきましたね。くそー!
宣伝会議賞2020、全体的な結果としてはこのような結果となりました。
一次審査、1本通過。
三次審査、1本通過。
上出来ではないでしょうか。
実は今回の宣伝会議賞、作戦を立てて臨んでいました。そしてその作戦が功をそうしました。
この記事では、応募したキャッチコピーと制作意図を振り返りたいと思います。他人の思考を覗き見る好奇心で構いませんので、最後まで読んでもらえるとうれしいです。
そして、キャッチコピーを考えるヒントになれば幸いでございます。
日本でいちばん有名なキャッチコピーの公募、宣伝会議賞とは?
そのコトバには、
※2020 宣伝会議賞キャッチコピーより
100万円以上の価値がある。
この記事を読んでいる人で宣伝会議賞を知らない人はいないと思いますが念の為、宣伝会議賞を紹介させていただきます。
グランプリ賞金は100万円
宣伝会議賞、グランプリは賞金100万です。
宣伝会議賞は、広告業界雑誌、月刊「宣伝会議」が主催する広告賞で、広告表現のアイデアをキャッチフレーズ・CM企画などの形式で募集しています。2020年は第58回目の開催でした。
現役のコピーライターが審査員を務めている
審査員は「仲畑貴志」さんをはじめ、日本を代表する有名コピーライターが名を連ねます
宣伝会議賞・歴代受賞者には「糸井重里」さんがいたり日本を代表するクリエイターがいたりと、名実ともに日本最大の公募と言っていいでしょう。
毎年秋頃に開催され、プロ・アマ問わず誰でも参加できる広告賞です。
キャッチコピーの応募総数がすごい
2020年のキャッチコピーの応募総数はなんと、
61万7203点!!
(※一般部門)
とんでもない数のキャッチコピー・広告アイデアが応募されました。
課題は、宣伝会議賞に協賛している企業による自社商品や自社サービス・企業メッセージやスローガンなど、広告アイデアを募る形式で行われます。
過去には「キッコーマン」「キンチョー」「SONY」など日本を代表する企業の参加がありました。
厳正な審査
応募されたキャッチコピーは、一次審査・二次審査・三次審査を通過で選考され、ファイナリストとして選出されます。そしてファイナリストの作品から、グランプリや協賛企業賞が決まります。
授賞式がある
授賞式は開催年の翌年に盛大に行われます。2020の宣伝会議賞は、女優「南 沙良」さんがイメージキャラクターを務め、表彰式にも出席されていました。
歴代のグランプリ作品は、宣伝会議賞の特設Webサイトから閲覧できます。https://senden.co/history
コピーライターの登竜門といわれ、広告業界ではあまりに有名な公募です。
実はぼく、宣伝会議さんが主催する「コピーライター養成講座」の卒業生です。
講座でコピーライティングを学んだことがきっかけで、宣伝会議賞を知り挑戦することにしました。
講座の講師陣には、宣伝会議賞の審査員をされているコピーライターがいて、宣伝会議賞のアドバイスを少しもらっていました。
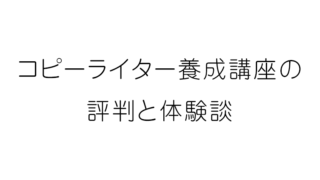
宣伝会議賞2020で書いたキャッチコピー
それでは三次審査・一次審査を通過したキャッチコピーを紹介したいと思います。
一次審査通過を通過したキャッチコピー
靴底をジャッキアップ。
課題 : セメダイン
シューズドクターNを使って、
引用:SKAT.20
すり減った靴底を直したくなる広告アイデア
制作意図
アイデア的には大喜利的な要素が強いキャッチコピーになりました。すり減った靴底を直すことが、車のジャッキアップに思えたので比喩として面白いと思ったのです。
三次審査を通過したキャッチコピー
握手は綺麗な手で
課題 : 社会情報大学院大学
企業の経営者が、<広報・PR>をもっと重視したくなるような
SKAT.20
<広報・PR>にかわる新しい言葉やフレーズ
制作意図
広報・PRに求められることは、顧客に向けて「自社をどのように受け取ってほしいか」情報を戦略的にマネジメントすることだと思いました。
社長にかわり会社のビジョンや理念を表現する役目があると考え、社長の言葉を顧客にわかりやすく、寄り添ったポジティブな言葉に変換しようと思っていました。
そこでコミュニケーションの観点から「握手」というキーワードを思いつき、そして広報は会社のいいところ・魅力を伝えなくてはと思い「綺麗」というワードに行きつきました。
宣伝会議賞2020・個人成績
三次審査の通過率は「0.02%」でした。
はじめての挑戦にして三次審査を通過したことは、評価していいのかも知れません。
宣伝会議賞2020「キャッチコピー部門」は全部で23課題。
個人成績は次の通りでした。
個人の結果
- 応募数 107 / 2300本中
- 応募課題数 7 / 23課題中
- 通過課題 2 / 23課題中
- 一次審査通過 2 / 107本中
- 三次審査通過 1 / 107本中
公募全体の結果
応募者全体で見ると次の通りです。
- 一次審査通過作品 5946点 / 通過率 0.99%
- 二次審査通過作品 605点 / 二次審査通過率 0.10%
- 三次審査通過作品 153点 / 三次審査通過率 0.02%
- ファイナリスト作品 24点 / ファイナリスト審査通過率 0.004%
※通過率は応募総数における割合
※ひとつの課題につき100本応募可能(2,300本応募可能)
※一般部門の数字
出典:宣伝会議2021年3,4月号 参照
ひとつの課題に集中して宣伝会議賞に挑戦した
「1本でもいいから、僕の書いたキャッチコピーが審査員の目に留まること」
これが、今回の宣伝会議賞の目標でした。
さっきお話しした通り、ぼくは宣伝会議さんのコピーライター養成講座に通っていました。
コピーライター養成講座の講師は、宣伝会議賞の審査員をしているコピーライターさんが数名いらっしゃいます。
他人と違う切り口を探そう
講師の方が宣伝会議賞の攻略法で口を揃えていうのは「応募されるキャッチコピーは、同じ切り口が大半を占めるから、すぐ思いつくような発想のコピーは審査員の目には留まらないと思った方がいいよ」とのアドバイスでした。
切り口とは「広告対象の良さ・メリット・ベネフィットを、どのような視点で表現し伝えているか」です。
約61万点ある応募作品の審査は、細かい表現を見るのではなく、まずは切り口を見るのだそうです。
裏を返せば、他の人と違う切り口のキャッチコピーは目立つわけです。他の応募者が思いつかない切り口を発見した時点で、審査はかなり通過しやすくなるのです。
キャッチコピー2,300本を書く常連組がいる
2020年の宣伝会議賞は、キャッチコピーの課題が23課題ありました。ひとつの課題に対し100本の応募ができ、上限数は2,300本、応募できることになります。
実際に宣伝会議賞に毎年挑戦している方の中には、今回の上限数、2,300本応募した方もいます。プロもアマも関係なく、数を書くことで確率を上げる戦略です。
でもぼくは正直「2,300本も書けない」と思ってしまいました。
いや確かに数を書くことは、それだけ思考している証拠なので勝率はあがるでしょう。
でも、まともに戦っても勝てないなと、感じてしまったのです。
ひとつの課題に集中することにした
そこでぼくは、キャッチコピーの数で勝負するのをやめ、切り口を探すことに時間をかける作戦に切り替えました。
さらに応募数が少ないと思われる「社会情報大学院大学」さんの課題を選択しました。
広報やPRの仕事は誰もが体験できる仕事ではないので、応募数が少ないだろうと考えたわけです。
一方、商品のキャッチコピーなど身近で取り組みやすい課題は、応募が殺到すると予想しました。たとえばキッコーマンさんの「豆乳」セメダインさんの「シューズドクターN」の課題がそれに該当します。
つまり競争相手を減らし、自分の書いたキャッチコピーが他の方の作品に埋もれないようにした作戦でした。
作戦が功を奏した?
結果「社会情報大学院大学」さんの課題で三次審査を通過しました。
コピーライター養成講座の講師の方々は口を揃えて「とにかくたくさん書け」と言います。数を考えることは思考の深さに直結するからです。小手先のテクニックよりも、考えた熱量とかけた時間が大事ではあります。
ただ、公募に関していえば短期決戦なので時間の使い方を工夫しなくては勝てないのかな?とも思いました。
キャッチコピーをどのようにして考えていったか
ここで、社会情報大学院大学のキャッチコピーをどのようにして書いたか。手順を整理してみようと思います。
本・雑誌・Web、とにかく情報収集をする
ずは以下の視点で情報収集をしました。
- 「広報・PR」とは何か
- 経営者はどんな思考で何を考えているのか?
ぼくは広報・PRの実務経験はありません。経営者になったこともなく、どのような視点に立って言葉を考えるべきかもわからない状態です。何の知識や情報もないのに発想が出てくる訳はありませんので、まずは調べます。
コピーライター養成講座の講師は「現場に行って取材してきなさい」といいます。現場に行き取材して肌で感じたことが、キャッチコピーになっていくのだそうです。
たしかに本人の実体験からなるエピソードや体験に基づいた感情には敵いません。でも実体験をすることは難しい。
ならば調べた量と時間で実体験を補うしかありません。書籍やWeb検索・経験者へのインタビューなどを通じて発想やアイデアを引き出し、周辺語彙を増やしていきました。
キャチコピーのコンセプトワードを決める
会社経営者は、広報やPRを「ブランディング」のために使いたいのでは?と考えました。
この時点で「顧客」「握手」「ポジティブ」などのコンセプトワードを書き出していたと思います。ぼくはマインドマップを使って言葉を連想していきます。
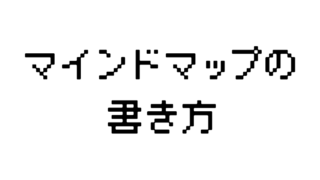
コンセプトに沿ってキャッチコピーを書きまくる
ひとつの課題に対して、とにかく書きまくりました。審査を通らなかったキャッチコピーをいくつかご紹介します。
語らないから、分かってもらえない。
自分の事をきちんと話せない人、
信用できますか?
分かってもらえないのは、
伝えてないから。
どんな奴か分かると、
友達になってくれるかも。
不祥事の後始末は、
スピードが勝負です。
芸人がひな壇で黙って座っていたら、
次から呼ばれなくなります。
社長が言うと身構える、
広報が言うと信頼できる。
メガホンみたいなものです。
いやぁ、これはさすがに恥ずかしい。審査通らないですよね。ボツもいっぱいあったわけです。
キャッチコピーは「選んで」「捨てて」「応募する」
候補を書き連ねたところで、応募するキャッチコピーを選んでいきます。
同じアイデアであっても、言い回しや句読点・語尾を変えたりすると言葉の表情が変化していきます。
- 書く
- 磨く
- 選ぶ
キャッチコピーはこれらのプロセスを経て応募されます。
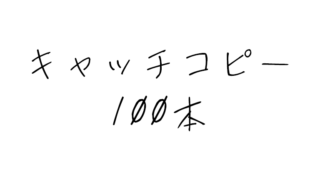
課題によってキャッチコピーを書き分けることの難しさ
宣伝会議賞の課題は、商品のキャッチコピーから企業スローガン、社会課題など多種多様です。
課題の性質によってキャッチコピーを書き分ける必要があるので、得意・不得意があるのかも知れません。
今回の課題を少し整理してみたいと思います。
「商品・サービス」の課題
- キッコーマン
- サントリー
- 商工中金
- 日本情報経済社会推進協会(プライバシーマーク)
「企業スローガン」の課題
- 関西電力
- 中部電力
- ショーエイコーポレーション
「世の中(社会)へのメッセージ」の課題
- 社会情報大学院大学
- クレディセゾン
- JT
- 楽天デザインラボ
個人的に「商品・サービス」の課題は、取り組みやすい課題だと感じました。
- 身近な商品だから購入・体験できる
- 消費者の声が検索できる
- ターゲットが想定しやすい
- 過去のキャッチコピーを調べやすい
宣伝会議賞2020の結果を受けて反省すべきところ
三次審査まで通過したことはうれしかったし自信にも繋がりました。しかし反省点も山のように出てきました。
応募したキャッチコピーの数が少ない・応募していない課題がある
今回応募したキャッチコピー数は、107本。
すべての課題に取り組み、上限の100本に応募すれば2,300本書けたはずでした。
応募していないことは、自分からチャンスを捨てているのと一緒です。とにかくなんでもいいから応募しておくべきですね。課題と向き合わなければ、技術や思考の成長はありません。
ひとつの課題にかける時間配分を考えるべきだった
宣伝会議賞は課題が発表されてから応募期限まで、ひと月半ほどの短期決戦です。
実をいうと最初は全ての課題にチャレンジするつもりでいました。まずは課題に対しての調査・リサーチをと思い書くのを後回しにしていたところ、とても時間が足りないことにきがつきました。
そこでチャレンジする課題を絞る作戦に切り替えました。
身近な商品のキャッチコピーほど難しい
まず、キッコーマン「豆乳」の課題に取り組みました。
- 商品を愛飲していていたこと
- 身近な商品で取り組みやすいこと
- 前年度の宣伝会議賞でも同じ課題が出題されていた
これらの理由で、考えやすいだろうと思ったのです。
しかし誰もが取り組みやすい課題はそれだけ切り口も出揃っています。他人とは違うキャッチコピーを書こうと商品の特徴を細かく調べすぎて、多くの時間を消費してしまいました。
ある程度調べたら、さっさっと書く方がいいですね。後で見直せばよかったんです。
過去の受賞作品を「SKAT」で見るべきだった
SKATは、前年の宣伝会議賞で一次審査を通過したキャッチコピーからすべて掲載されている単行本です。宣伝会議賞翌年に発行されます。
プロアマ問わず応募できる宣伝会議賞は、電通をはじめ有名企業のコピーライターも同じ土俵で戦っています。
SKATを見て多くの作品にふれておくと、課題の傾向や審査の基準・キャッチコピーのアイデアを知ることができます。
パクリは禁止ですが、キャッチコピーが出てこない時、眺めていればヒントになったりしますしアイデアの仕組みは真似してもいいと思います。
キャッチコピーの書き方を体系化する
闇雲にキャッチコピーを書いていても、いいキャッチコピーは書けないのかも知れません。自分の中で、論理を組み立てる必要があると思いました。
コピーライター養成講座の講師は現役のコピーライターさんばかりです。だいたいの講師の方は、独自の理論を持っていました。誰一人として同じ書き方をしていませんでした。
ぼくは今回、広告対象を調べながら関連語句・語彙を集め、それらの言葉から連想してアイデアや発想を広げていきました。
一定のクオリティーを保つためには、思いつきやひらめきで書かず、論理的なアプローチが必要ですね。
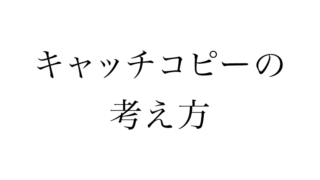
「SKAT.2020」自分の書いたキャッチコピーが掲載されました
一次審査を通過したキャッチコピーは、翌年のSKATに掲載されます。書籍に自分の名前が載るのは素直に嬉しいですね。
宣伝会議賞に挑戦してみて
宣伝会議賞は、本気で取り組んでいるコピーライターの方も一緒の土俵で戦います。
グランプリを狙って結果を出すことで。将来が開けることもあるかも知れません。自分の実力を知るいい機会になるし、結果が出れば自信に繋がります。
本気で宣伝会議賞に取り組み熱くなるのは、素敵なことだとぼくは思います。
ですが、素直に公募を楽しむことも大切です。
最後に、宣伝会議賞に挑戦したみなさまへ。
お疲れ様でした。